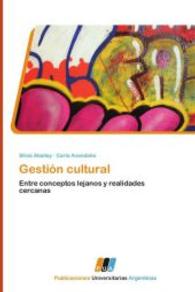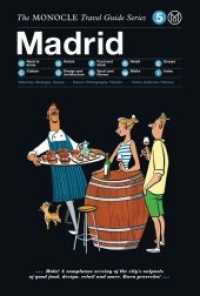出版社内容情報
広汎な農村実態調査をもとに,日本の家父長制家族と社会の改革の道を探り,戦後社会科学の出発を画した代表的論稿.「イデオロギーとしての『家族制度』」を加えた新編集版.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Olive
10
日本の社会と家族・家族的結合にはどのような思想があり、その思想が時代と共に(主に中央によって統制され)変化していったのかを、養子や教育など多面的にとらえようとする。 そしてイデオロギーとしての「孝」や「家族制度」が「忠」という時代を逆行する思想になっていった歴史的背景のもと、資本主義の発展によって、家族制度イデオロギーにどのように思想が代替されていったのかがわかって面白かった。国民の基本は「家」という現在も抜け出ることができない国民性の基本を作り出した根源を追求する本。2023/04/20
K.H.
4
「日本社会の封建遺制」などと時々言われるが、本書を読んで驚いた。筆者は近代日本の(武士階級を範とした)家族制度、およびそれとの類推・擬制を通じて作られた戦前の国家は、権利の当事者意識が希薄な、封建的とさえ言い難いものだったという。あるいは常識なのかもしれないけれど、封建的にも未成熟というのはわたしとしては新鮮だった。そしてこの「前封建的」家意識は、部分的にせよ今日までなお引きずられているように思われる。ところで筒井先生の解説は何かズレているように感じられたが、挙げられている文献を読んでいないので、まあ…。2021/10/24
亀山正喜
0
小室直樹「痛快憲法学」→川島武宜「日本人の法意識」→本書。p166 〜が個人的にハイライト。明治政府は武士社会の統治から何を持って国を統治するかという問題に当たり、武士社会で馴染みのあった儒教的教義の忠孝をアレンジすることで対応した。父母を最大限敬うこと、父母の先祖は神であるとして、父母の尊貴を神によって根拠づけると同時に、神に対する信仰を孝の拡大として構成した。そして神の直系である天皇とつなげ、天皇と人民の関係を父母と子の親子関係に類推することで「天皇の親心」といった心持ちを国民に持たせた。なるほど。2025/11/04
くまきん
0
本書の著書は民法、法社会学を専門とする法学者であり、出版されたのが1950年で戦後の民法改正時である事も考慮に入れて読まねばならないが、日本が持っていた旧弊な封建的家族制度の特徴と欠陥を見事に分析している。 所謂日本の伝統的家族制度は、支配階級の慣習になっていた、権威と恭順を基本原理としたものであり、自発的な人格の相互尊重による家族制度とは対極的なものである。それは封建的武士階級の発生とともに自然成立したものであると思えるが、江戸時代にはその武家の伝統を元に儒教的な味付けをした「道徳」ととしての→ 2023/11/06
劇団SF喫茶 週末営業
0
戦後日本の進歩的文化人とはなんだったか。それは欧米のモノマネをすることである。進歩というのは欧米化されているということだ。本書は「欧米の視点」から戦前の日本を断罪し告発する書である。確かに日本の家族構成の分析には妥当な部分はある。しかし問題は、それらを全て破壊し日本を脱却して世界市民になろう!という根本的な思想が空疎なものでしかないところだ。日本は家族制度を否定し「おひとりさまの老後」にたどり着いた。だが、憧れていた欧米社会には家族制度は強固なものとして残っている。2022/03/05