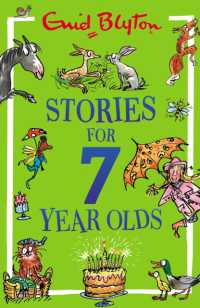内容説明
2020年度の教育改革をひかえ「主体的・対話的で深い学び」「探究型学習」「哲学対話の授業」などへの関心が高まっています。正解のない課題に対して自分で「考える」ことがますます求められるようになります。本書ではフランスの事例を紹介しながら、「考える」について考えます。
目次
プロローグ 『アンパンマンのマーチ』の先へ
第1章 「ひとり」を大切に(「哲学」という日本語―孤独になる、自分で答えを見つける;個人主義の保障・推奨―憲法十三条を知っていますか;「群れる」ことがいじめを生む―いじめにあっても自分を愛し続ける ほか)
第2章 「考える」を大事にする(幼稚園の教科書―ラ・フォンテーヌの寓話詩;セ・ラ・ヴィ(それが人生よ)―だれもが哲学者
哲学授業の広がり―十八歳までに ほか)
第3章 想像力を大事にする(絵のない絵本と絵だけの絵本―想像力を刺激し考えさせるもの;マルク・シャガール―ベラ作品と「パリ・オペラ座の天井画」;ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト―オペラ『魔笛』 ほか)
-
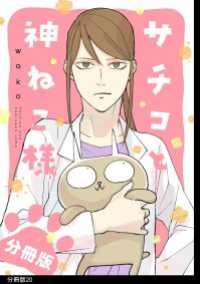
- 電子書籍
- サチコと神ねこ様【フルカラー】分冊版(…
-
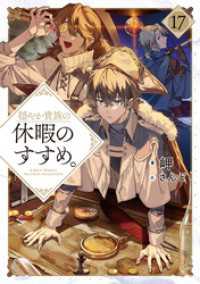
- 電子書籍
- 穏やか貴族の休暇のすすめ。17【電子書…