出版社内容情報
社会の一員として〈情報〉を受け取り,加工し,発信していくだけではなく,より社会と密接なかたちで〈情報〉をとらえるためには何が必要なのだろうか.目に見えない力〈情報〉と正しくつきあうためのヒント.
内容説明
「情報リテラシー」「情報化社会」とはどういうことなのだろうか。たくさんの情報機器の中で生きている私たちが、“情報”を受け取り、加工し、発信していくだけではなく、より社会と密接に“情報”をとらえていくためには、何が必要なのだろうか。目に見えない力“情報”と正しくつきあうためのヒント。
目次
1 情報を扱う技術(情報とは;情報を計測するには ほか)
2 情報の力と社会(世界を変えた一ビット―ワーテルロー・スクープと情報;情報を扱うビジネス ほか)
3 情報が世界を動かす(政治宣伝という情報;ゆがんでいく情報)
4 情報の消費者として
著者等紹介
春木良且[ハルキヨシカツ]
1956年生まれ。東京大学工学系研究科博士課程単位取得期間満了退学(先端学際工学専攻)。民間企業でソフトウェア開発、コンサルティング、教育などに携わった後、現在、フェリス女学院大学国際交流学部助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
iwtn_
5
この新書は高校生向けのシリーズなんだけど参考になる。特にアメリカン航空の予約システムの戦略性については、こういう視点で考えて戦略を立てているか?と言われると、そうじゃないなって思う。技術的な内容も2進数や半加算器・全加算器の仕組みまで書いてあるので、とても良い。最後にある、目の前の人と話しているときに携帯電話に出るか?は、むしろ技師が進んだ結果、かなり緊急じゃないと電話が来ないので、今なら出るかもしれない。その他情報の重要性をワールテローの戦いなどの面白い話題でまとめているので、読んでよかったと思う。2022/11/23
nagata
4
中高生向け、しかもテーマからしてもやや古い本に属するだろうが、学ぶところは多い。そもそも情報は…から説き起こし、読み書き能力≒リテラシーの中身をより具体的に示しているから、その先のイメージが鮮明になる。何も機器の操作に習熟するだけではなく、何が問題なのかを見定めて、何が必要なのかをつかんだうえで各方面から情報を集め、どう分析していくかが大切なのだと思う。2024/07/28
affistar
2
2004年に出版された本です。技術面で書かれていることはTCP/IPやIPアドレス、DNSなどで現在と全く変わっていません。ゆがんでいく情報として、うわさ・流言・都市伝説をあげています。チェーンメールなどが例としてあがっていて、それは確かに古い印象がありますが、本質的なところでは変わってないと思います。情報の意味を読み取り、情報とうまくつきあおうという提言は、現在でも通じるところがあります。情報を鵜呑みにせず、それって本当かな、問題の本質はどこにあるのかな、と一旦立ち止まることが大切だなと思います。2021/09/30
takuchan
2
政治的な意図のない映画に政治的な意図を込めて見られたくないという意図が、逆に政治的な意図になってしまっている/尼崎事件の顔写真間違えやiPS森口氏報道・橋本市長報道など、メディアの情報の訂正・お詫びが増えている今こそ読むべき本だと思います。2012/11/02
カラス
1
そもそもにおいて、情報とはなにか?、などと考えたことがなかった。だから、情報とはなにかという定義から始まって、コンピューターの成立までを描いたはじめの章「情報を扱う技術」はとても興味深かった。未知が既知になるのが情報、そして情報の最小単位は二択、これが1ビット。そして発明から三百年の時を経て二進法がコンピューターの成立に寄与するという壮大な伏線回収。コンピューターの基礎の基礎を知るのがとても楽しかった。2019/03/20
-
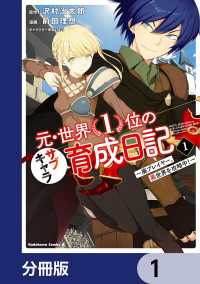
- 電子書籍
- 元・世界1位のサブキャラ育成日記 ~廃…
-

- DVD
- ハンテッド





