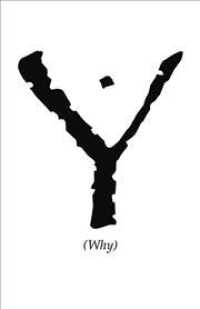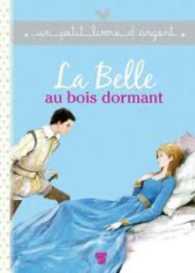出版社内容情報
文学は戦争を抑止するために何ができるのか。連合国による戦争裁判が終結した後も、日本文学は、法が裁けなかった罪を問い直し、戦争の暴力に向き合い続けてきた。一九四〇年代後半から現在まで、時代の要請のもとに生み出されてきた、戦争裁判をテーマとした主要な作品と作家を取り上げて、新たな文学史を描く。
内容説明
文学は戦争を抑止するために何ができるのか。連合国による戦争裁判が終結した後も、日本文学は、法が裁けなかった罪を問い直し、戦争の暴力に向き合い続けてきた。一九四〇年代後半から現在まで、時代の要請のもとに生み出されてきた、戦争裁判をテーマとした主要な作品と作家を取り上げて、新たな文学史を描くことに挑む。
目次
第1章 東京裁判と同時代作家たち
第2章 BC級裁判が突きつけたもの(一九五〇年代)
第3章 裁かれなかった残虐行為(一九六〇年代)
第4章 ベトナム戦争とよみがえる東京裁判(一九七〇年代)
第5章 経済大国と混迷する戦争裁判観(一九八〇年代)
第6章 記憶をめぐる法廷(一九九〇年代から二〇〇〇年代)
第7章 戦争裁判と文学の今と未来(二〇一〇年代以降)
著者等紹介
金ヨンロン[キムヨンロン]
1984年韓国ソウル生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。日本近現代文学専攻。現在、大妻女子大学文学部専任講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hasegawa noboru
22
戦後日本文学は戦争裁判をどう描いているかをテーマに主要作品を数多く取り上げながら丁寧に検証している。いかに日本近現代文学研究家とは言え、韓国の若い才媛によってなされていることにまず驚かされる。浅学の身を恥じるのみ。なにしろそこに論じられている作品のほとんどを読んでいないのだから。今進行中のウクライナ、イスラエル軍ガザ地区侵攻の惨たらしい暴力殺人の状況がまず思い浮かぶ。現実の戦争と文学の有効性という繰り返されてきた重い問いのことが次に浮かぶ。国連機関が、自国が自国の戦争を、審判することも望むべくもない。 2023/12/26
やまはるか
21
東京裁判は日本の共産化を警戒したアメリカによる不徹底な追及に終わった印象は本書でも変わらない。A級戦犯で東条英機の頭を叩き精神異常により免訴となった大川周明を主人公にした松本清張「砂の審廷」は是非読んで見たい。「落日燃ゆ」で取り上げられた背広組のA級戦犯広田弘毅の、長州が作った「統帥権の独立を認めた明治憲法が、いつか大きな禍となる」との言葉、占領下での検閲のもとで発信されたものを「奴隷の言葉」と呼ぶ江藤淳のノンフィクションなど印象に残った。従軍慰安婦に関する川田文子の著作は我が街の図書館に一冊もない。2024/07/14
真琴
12
東京裁判、BC級裁判が終結した後、文学により作家は戦争の暴力と向き合ってきた。本書は、林芙美子『浮雲』遠藤周作『海と毒薬』井上ひさし『夢の裂け目』といった戦争文学を読み解いている。戦争裁判を取り上げる作品は残虐行為に対する証言文学でもある、と言う点が興味深かった。2023/12/04
チェアー
10
筆者は、戦争文学を「世界文学」の視野で読むことを提唱している。専門家が、精緻に読み込む手法ではなく、一般の人が翻訳などで他国の戦争文学を読み、自分の国の戦争の歴史や文学にフィードバックしていくということと理解している。 2024/01/08
みなみ
7
Unlimitedで読了。東京裁判の小説がこんなにあるとは知らなかった!でも新型コロナウイルスも小説に登場するし、社会に強く影響を与えた出来事は文学になるんだろうな。色々読んでみたい。松本清張は戦前を舞台にした小説も書いているからなんか納得。同時代の小説だけでなく、1980年代以降、近年の小説まで題材にしているのが良かった。2025/09/13
-

- 洋書
- A Roman Wit