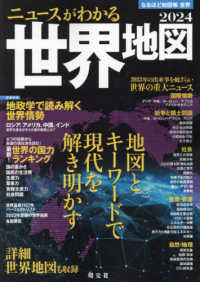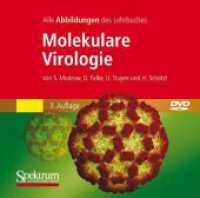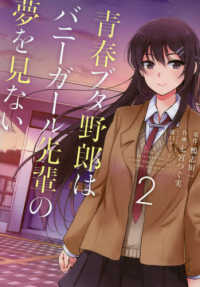出版社内容情報
衣食住から信仰に至るまで、日本の歴史とは、木とともに歩んだ歴史であるといっても過言ではない。森のめぐみを享受した先史時代、都城や寺院などの大量造営が展開した古代から、森との共生を目ざす現代まで――建築のみならず流通にも着目し、また考古・民俗・技術などの知見も駆使して、人びとが育んだ「木の文化」を描く。
内容説明
衣食住から信仰に至るまで、日本の歴史とは、木とともに歩んだ歴史であるといっても過言ではない。森のめぐみを享受した先史時代、都城や寺院などの大量造営が展開した古代から、森との共生を目ざす現代まで―建築のみならず流通にも着目し、また考古・民俗・技術などの知見も駆使して、人びとが育んだ「木の文化」を描く。
目次
序章 日本の森林と木の文化
第1章 木と人のいとなみ
第2章 豊かな森のめぐみ―古代
第3章 奪われる森と技術のあゆみ―中世
第4章 荒廃と保全のせめぎあい―近世
終章 未来へのたすき―近代から現代
著者等紹介
海野聡[ウンノサトシ]
1983年、千葉県生まれ。2009年、東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程中退。博士(工学)。奈良文化財研究所を経て、東京大学大学院工学系研究科建築学専攻准教授。専門、日本建築史・文化財保存(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひろし
73
古いお寺に行くと、この建物は何百年経っていて全部ヒノキでできている、などの説明をよく聞く。日本の昔の建物は、ほとんど木でできているからである。時代が古いほど巨大な材料に依拠していて、奈良の古寺では柱や梁が太く立派。その頃は巨材が身近な山で入手しやすかったということがある。その後、森林資源の枯渇と技術革新が並行して進み、以前より細い材料でも大きな建物が建てられるようになったそうだ。2022/07/24
tamami
52
文字通り『森と木と建築の日本史』である。本書の表紙裏には、「衣食住から信仰に至るまで、日本の歴史とは、木とともに歩んだ歴史である…」と書かれているが、話題が衣食住に及んだのは主として第1章で、そこは大変興味深く読ませてもらった。第2章以下は、専ら著者が専門とする古代以来の寺社を中心にした建築で使われた材としての木の話が中心で、やや一本調子な印象を受ける。原始潤沢であった日本の森林資源にも、古代以来の乱開発の影響で陰りが見え、中世以降は新たに原木探索の範囲を広げたり、大口径の材を求めてヒノキ以外の樹種にも手2022/04/25
山口透析鉄
35
以前買っていた積読本より。日本列島と木造建築の関係が時系列的に述べられていて神社仏閣について詳しくないので勉強にもなります。 古代の狩猟採集時代の描写に始まり、法隆寺や東大寺の建設に伴う大木(信仰の対象でもあり、諏訪の御柱が詳述されています)がやがて払底はするものの、技術革新で精密な建築物も作れるように変わっていく様が活写されています。 森林の伐採は戦国時代以降も続いていて、計画的な植林まで結構な時間がかかっています。 現状の林業は衰退していますので、良いところはあまりなさそうでした。一次産業も重要です。2025/06/12
gotomegu
13
古代からの歴史的な建築物。大きな建物は巨木をつかう。建てていくうちに木材が足りなくなって、遠いところから運んでくるようになる。樹種を変えて作ったり。運搬は川と海から。巨木は船に載せるだけでも大変だっただろう。近年は台湾やカナダなど海外から運んできている。植えて育てていたのは奈良や秋田などごく一部だったのが意外。木曽や伊勢はなかり最近になってからだった。今後は海外から調達するのも難しくなるだろう。国内でちゃんと計画的に植えて育ててるのかな?2023/01/14
不純文學交遊録
11
日本は国土の7割が森林で、前近代の建物はほとんどが木で造られてきた。日本の歴史は、木の文化の歴史である。しかし藤原京や平城京が造営された時代から、森林資源の枯渇は始まっていた。建築技術が未熟な古代は、太く長い柱や一枚板の扉など、建物の構造を材料そのものの強度に依存した。中世には近畿周辺の山林での巨材の入手は困難になる。森林の保全から育成へと転換するのは明治以降である。巨木の育成には数百年を要し、規格外の巨材は流通する市場もない。将来の文化財修理に備えた森林の確保と技術の継承が急務となっている。2022/08/12
-
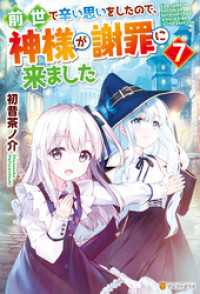
- 電子書籍
- 前世で辛い思いをしたので、神様が謝罪に…