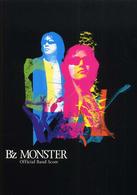出版社内容情報
西行の「桜」、親鸞の「悪」、長明の「無常」──。5つのキーワードから、日本文化の根底にあるものの見方、美意識のあり方を素描する。
内容説明
異なる文化のあいだでの腰を据えた“対話”がますます求められる時代。そのための基礎的な知識として、西行の「心」、親鸞の「悪」、世阿弥の「花」など5つのキーワードから、日本文化の根底にあるものの見かた、美意識のありかたを素描する。西田幾多郎の思想をヒントに、日本文化のひとつの“自画像”を描く試み。
目次
第1章 西行の「心」―無常の世と詠歌懸命の道
第2章 親鸞の「悪」―末法の世における救い
第3章 長明と兼好の「無常」―二人の遁世者
第4章 世阿弥の「花」―能と禅の交わり
第5章 芭蕉の「風雅」―わび・さびと「自然」
終章 西田幾多郎の日本文化論―世界主義という視点
著者等紹介
藤田正勝[フジタマサカツ]
1949年三重県に生まれる。1978年京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。1982年ドイツ・ボーフム大学大学院ドクター・コース修了。専攻―哲学、日本哲学史。現在―京都大学大学院総合生存学館教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こぽぞう☆
13
西行、親鸞、長明と兼好、世阿弥、芭蕉の五章からなる日本文化論。全てを貫くのは「無常」なのだけど「無常」だけが日本文化?となった。また、彼らの残した文章から思想を取り出しているが、彼らのうち何人かの伝記を読んだ者としては、それだけでいいのか?とも思った。2019/03/17
politics
8
西行、兼行、世阿弥、芭蕉らの文芸から日本文化の基底・美意識を掬い出し、最後に西田幾多郎の日本文化論からいかに日本文化を論ずるかの方法論を検討した一冊。取り上げられたものの共通点として無常や虚無感、生死などがキータームとなっており、これらは著者も連なる京都学派の哲学者が論じた点と共通し、日本文化の中にいかに哲学的要素が多いかが改めて確認できる。文学・思想・哲学の三つの領域が日本では密接に関係し合っている事が理解でき、相互に参照し合いながら学習することが重要なのだろう。2023/06/21
みつ
7
世界のグローバル化の中、異なる文化や思想との「対話」を意義あるものとするため、明確な「自画像」を描く必要がある。・・・序で著者はこのような趣旨を述べ、「心」「悪」「無常」「花」「風雅」の5つのキーワードと、それぞれが結び付く5人(西行、親鸞、兼好、世阿弥、芭蕉)の思想を辿る。著者自ら断っているように、ここで触れられるのは、あくまでも日本の詩歌や芸術、宗教の歴史そのものであり、それらが広い意味での日本文化にどのように影響を与えたかは不明。終章にある西田幾多郎の提唱する多文化創造への歩みは、読み取れずじまい。2021/06/01
sk
6
西行、親鸞、兼好、世阿弥、芭蕉の思想を紹介。日本の伝統を知るのによい本かも。2019/01/22
oooともろー
6
西行・親鸞・芭蕉…日本文化に通底する無常観。グローバル化の中での日本文化のあり方。今だからこそ西田幾多郎の文化論が光る。2018/03/21
-
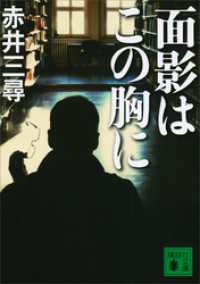
- 電子書籍
- 面影はこの胸に 講談社文庫