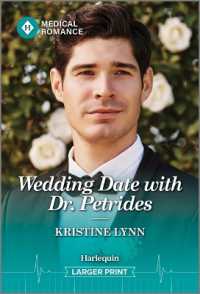出版社内容情報
日々の「ごみの行方」は?最新のリサイクル施設、海を渡った中古品、拡大している最新のリユース事情などを活写。
内容説明
日本のごみは年間約四億二〇〇〇万トン。分別収集やリサイクルが奨励され、最新型の焼却炉は環境に配慮されるようになっている。しかし日々の「ごみの行方」はどうなっているのか。最先端のリサイクル施設、不法投棄の現場、海を渡った中古品、関連法施行の背景、拡大するリユース事情などを長年取材を重ねてきた著者が活写。
目次
序章 にっぽんのごみ
第1章 ごみはどこに行っているのか?
第2章 リサイクル大国の真実
第3章 市民権を得て拡大するリユース
第4章 ごみ事情最先端
第5章 循環型社会と「3R」
著者等紹介
杉本裕明[スギモトヒロアキ]
1954年生まれ。早稲田大学商学部卒。1980年より2014年まで、朝日新聞記者。廃棄物、自然保護、公害、地球温暖化、ダム・道路問題など環境問題全般を取材。環境省、国土交通省、自治体の動向にも詳しい。現在はフリージャーナリスト。NPO法人未来舎の代表理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やすらぎ
137
ゴミを棄てる。欲しいものを手に入れるときは慎重に考え、大事なお金と引き換えに自分のものとするが、いずれ不要となり棄てるときにお金を取られることに抵抗し、ぽいっと投げ棄てる。…本書にはあらゆる取り組みが記されている。若干難しいが、読後は物を買う=ゴミを買う、廃棄費用の一部を消費者が負担するのは当然のことという認識になる。…私たちの源の森に不法投棄、生け垣にゴミを投げ、排水溝に吸い殻を。道端にはマスクが散乱。棄てる人は棄て続け、拾う人は拾い続ける。ごく一部の人が棄てたゴミで嫌な思いをしている困った社会である。2021/03/12
mazda
29
フィリピンに輸出される中古電化製品、廃プラスティックを化学リサイクルし燃料に変えるプラント、徹底したゴミ減らしによるコスト削減に成功した自治体、リサイクルが増えたことで、逆に燃やすゴミがなくなって困っている焼却炉を持つ自治体。以外にリサイクルは形になっているんだなというのが、率直な感想でした。2016/10/23
hamao625
19
普段は分別収集方法に従い、捨てているゴミ。その後のことは気にしていませんでしたが、問題山積みだということがわかりました。日本のごみは年間約4億2000万トン。桁が凄すぎてピンときません。それなのに焼却施設をもてあましている自治体も多いとか。それに嫌われものの焼却灰はどうなっているのでしょうか?資源になるといわれるリサイクルはコストがかかる。効率のいいリサイクルができるようになるときは来るのか?コストが下がれば変わってくるのでしょうか?この先、ゴミやリサイクル事情がどうなるか心配になります。2015/08/29
501
18
リユース、リサイクル、焼却ごみがそれぞれどこに流れ処理されるか、その仕組みに絡む各省庁、業界の利権の構造を追う。たかがごみ、されどごみ。本書は普段ごみを捨てるという日常の行為の向こう側に広がる奇怪に複雑な日本のごみ事情を俯瞰できる。日本のごみ事情の問題点は何なのか明らかにする点は弱い。ごみ問題の目的は環境保全にあるはずだが、利害が絡むものだけに奇怪な体をなしてしまうのが現代社会の悲しさ。2016/05/15
マッキー
17
ゴミの取引現場のあまりにも複雑な世界が書かれていた。我々の知らないところで法律や条例がたくさんできている。一番面白かったのはリユースについての項目。身近な話題だし、フィリピンのテレビのことやハードオフのことなどを読んで、中古市場の規模の大きさに驚いた。2016/02/07
-
- 洋書
- Genesis