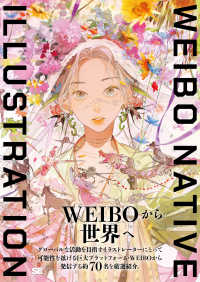内容説明
「最近、よく転ぶようになった」。そう感じたら要注意。転倒はいのちに対する身体からの黄色信号です。いつまでも丈夫な足で歩きつづける。転んでもケガをしない。ラジオや講演の明快解説で評判の著者が、暮らしのなかでの心がまえと、転倒に負けない身体づくりの基本を指南します。自信と希望をもち、生きる力を取りもどすために。
目次
第1章 歩くとは
第2章 転ぶとは
第3章 転ばぬ先の杖
第4章 転ばぬ先の知恵
第5章 今どきの転倒事情
終章 人生七転び八起き
著者等紹介
武藤芳照[ムトウヨシテル]
1950年生まれ。1975年、名古屋大学医学部卒業。東京厚生年金病院整形外科医長、東京大学教育学部長、同大学副学長などを歴任。ロサンゼルス、ソウル、バルセロナ五輪、水泳日本代表チームドクター、国際水泳連盟医事委員なども務めた。東京大学政策ビジョン研究センター教授をへて、現在、学校法人日本体育大学日体大総合研究所所長、東京大学名誉教授、転倒予防医学研究会世話人代表。専攻はスポーツ医学、身体教育学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
14
字体が大きい。読者を高齢者に想定しているためだろう。歩行者用信号が青のうちに、渡り切れるか、どうか(12頁の実験では平均7秒)。これは、高齢者になって体験しないと危ない目に遭う。転倒恐怖者が陥った悪循環とは、精神的な不安→自己過小評価→閉じこもり→身体機能低下→ふらつく・・・などという中で、実際に転ぶ(34頁)。認知症は転びやすい(134頁)。転んでしまうと、死に一歩近づいたことになるよう印象を得た。転んでも起きればいい、とはいうが、呆けて転んでなら家族や他人に多大な迷惑がかかると痛感した。2013/11/11
ともたか
7
「転倒は命の黄色信号」。転ばぬ先の杖ではなく 体操または歩け歩けかな。2016/07/16
izw
6
AITC(http://aitc.jp/)で「空気を読む家」という名の下にIT活用して家を快適にできないかと考えている。今年のテーマは危険予防。議論をする中で転倒防止と火傷防止にフォーカスすることになった。転倒防止を考える中で「日本転倒予防学会」という学会を見つけ、そのHP http://www.tentouyobou.jp/ に掲載されていた書籍をいくつか読むことにした。まずは手軽な新書から読んでみた。年をとると筋力低下、バランス障害、歩行能力低下などで転倒リスクが増える。今後気をつけないといけない。2019/09/04
みらい
2
「転んだら、起きればいいや」という心持が核心をついているように思います。もちろん、何事も転倒予防は大事。2016/03/28
ookumamasa
1
実家で独り暮らししている母が散歩帰りに門の段差で転倒して、左足首にひびが入ってギプス生活。長男としてギプス外れるまで付き添っている間に買い置きしていたものを読み終えた。 ★転んでも起きればいいや! 長い人生、身体も心も「転ぶ」ことはある。具体的な転倒予防のノウハウから「転ぶ」と言うことの奥の深さまで触れられた好著。2015/11/03