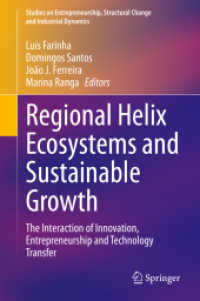出版社内容情報
権力争いの結果として予期せず皇位についた桓武は,王統の革新を強調すべく二度の遷都を行った.天皇を中心とした統治システムがしだいに安定するにつれ〈イエ〉意識が誕生し,いっぽう宗教や文学など背景となる時代精神も変化してゆく.長らく〈国風文化〉の源とされてきた平安朝の実像はいかなるものだったか.
内容説明
権力争いの結果、予期せず皇位について桓武は、皇統の革新を強調すべく二度の遷都を行った。以後長らく日本の都として栄えることとなった平安京。その黎明期、いかなる文化が形成されたのか。天皇を中心とした統治システムの変遷や、最澄・空海による密教の興隆、また地方社会の変化にも目配りしつつ、武士誕生の時代までを描く。
目次
はじめに―平安時代を脱ぎ、着る明治天皇
第1章 桓武天皇とその時代
第2章 唐風化への道
第3章 「幼帝」の誕生と摂政・関白の出現
第4章 成熟する平安王朝
第5章 唐の滅亡と内乱の時代
第6章 都鄙の人々
おわりに―起源としての一〇世紀
著者等紹介
川尻秋生[カワジリアキオ]
1961年千葉県生まれ。1986年早稲田大学大学院文学研究科修士課程史学(日本史)専攻修了、千葉県立中央博物館上席研究員を経て、現在は、早稲田大学文学学術院教授。博士(文学)。専攻は日本古代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まえぞう
24
5巻目は摂関時代以前の平安時代です。奈良時代に完成を見た律令政治が次第に崩れていき、中世を用意するなかでの動きが語られます。後書きでもありますが、奈良時代と比べてメリハリがハッキリしなくて分かりづらいという感想は私も持ちました。2025/06/09
びっぐすとん
19
図書館本。平城京で出来た日本という国の方向性が決まったのが平安京かな。明治維新と同じく闇雲に先進文化を吸収した奈良時代。自分達なりに消化し、独自路線を歩みだし、やがて円熟し綻び始める平安時代。地方に無関心なのは今の政治も同じ。緊張感がなくなると末端から腐り始め、収束がつかなくなると歴史は語っているのに。同じ骨肉の争いで肉親が死んでも怨霊騒ぎなどなかった奈良時代に比べ、怨霊におののく平安の皇族、貴族。平安時代人がやわになったのか、より繊細な感情が芽生えたのか、心理や価値観の面でも奈良時代とは違うようだ。2019/12/11
えいなえいな
18
平安時代は重要な時代だと思ってましたが、作者の方も言っているように世の中的にはそれほど認められていないそうで意外でした。日本人は自分たちの起源を平安より前の飛鳥とか奈良時代に求めるそうです。そうは言っても読んでみて思ったのは今の時代のルーツになる部分が平安時代にはあったんじゃないかな、ということです。かな文字や神仏、外交に関してのことなんかも、今のように完成されたものではないでしょうけど、400年続いた中で文化的なものに向かう姿勢というのは強かったんじゃないかなと思います。その辺り現代に通じませんかね?2019/11/22
coolflat
14
694年長岡遷都(桓武天皇)から969年安和の変(冷泉天皇)までを扱っている。150頁。9世紀後半以降、税の納入期限の遅れ、未納や粗悪化が問題となった。このことは、律令国家に深刻な問題を引き起こした。特に顕在化したのは国司の徴税の怠慢や横領であった。この対策として生まれたのが受領国司制である。国家は、受領にもっぱら徴税や検察を任せる代わりに、国務に直接口出しすることを控えるようになった。受領国司の権限は、それ以前と比べて飛躍的に強化されたと同時に、国家が直接地域社会を統治することを放棄したことになる。2017/04/09
fseigojp
13
前半は、蝦夷との38年戦争 後半は、幼年天皇の登場2020/03/24