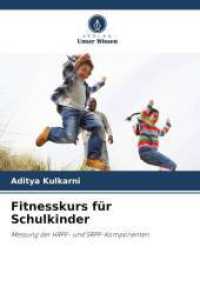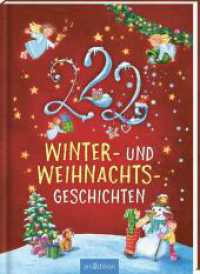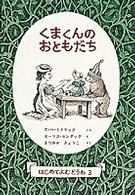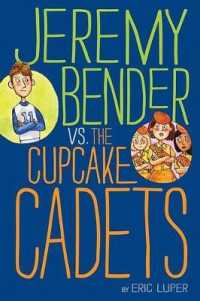内容説明
『古寺巡礼』『風土』等、流麗な文体により、かつて青年の熱狂をかきたてたことで知られる和辻哲郎。彼は同時に、日本近代が生んだ最大の体系的哲学書、『倫理学』の著者でもある。日清戦争前夜に生まれ第二次大戦後におよんだその生と思考の軌跡は、いかなる可能性と限界とをはらむものだったのか。同時代の思想状況を参照しつつ辿る。
目次
序章 絶筆
第1章 ふたつの風景(故郷;離郷;帝都)
第2章 回帰する倫理(回帰;渡航;倫理)
第3章 時代のなかで(時代;国家;戦後)
終章 文人
著者等紹介
熊野純彦[クマノスミヒコ]
1958年神奈川県に生まれる。1986年東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。専攻は倫理学、哲学史。現在、東京大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
89
私と和辻のつながりは中学時代に「古寺巡礼」を耽読したことに始まります。今までに何度読んだかわからないくらいです。そのほか「鎖国」「風土」「人間の学としての倫理学」などは結構何度も読み返しました。その和辻についての思想遍歴と評伝です。新書版によく収めたというくらいに簡潔にまとまっています。本当は大著の「倫理学」を完読したいのですが挫折しています。2015/09/08
Ex libris 毒餃子
9
原典に触れないとわからんなあ。2023/01/06
グスタフ
9
古寺巡礼などの、自然や芸術への豊かな表現力には圧倒される。日本語の美しさ。しかしその独自の文体の魅力は、錯誤とも分かちがたいものであることも、熊野氏は鋭く指摘する。つまり間違っているけど、美しい。でも、美しければそれでいい。だが、一方和辻の西欧哲学に関する論評、例えばハイデッガー批判などは、だいぶピントがずれていて許容範囲外。「哲学することが、ギリシア以来の普遍的な思考の水準に参与することなら、日本語で哲学することは、日本語の固有性をむしろ抹消する。」(熊野)ことを考えさせられ思い知らされる本。 2014/05/17
tieckP(ティークP)
7
いやあ、素晴らしい。この小著は、詩情と無類の読解力を併せ持った熊野純彦による、和辻とその哲学のラッピングだ。ある作品が美しいと思う根拠に、天才がその才能を十全に発揮していることを挙げてもあまり反論されないと思うが、この小さな新書は、和辻が様々な哲学に触れながらそれへの反応として哲学書・随筆を書いてきた過程を見事に整理し、和辻に対するその後の日本人研究者の言及を全て理解して効率的に挿入し、かつ序章と終章は和辻の美的感性をその水準のまま美的に読者に届けており、熊野氏の才能でしかできないと納得させられる。2021/11/11
K.H.
6
和辻哲郎の伝記として面白く読めた。また、本書が明らかにしようとしている、和辻がその思想的立場、特に『倫理学』の体系と不即不離の生き方をしていたというのも、ある程度納得できた。だけど、どうもそれ以上の感興が薄い。和辻に対しては学問的側面でも思想的側面でも批判が多いが、それらについては紹介や示唆に留まっていて正面から取り組んでいないように見えるからだろうか。もっとも、そういう本ではないと言われればそれまでなのだが。2022/01/08