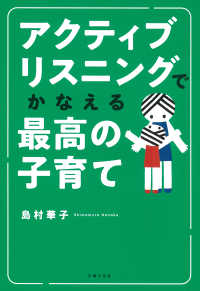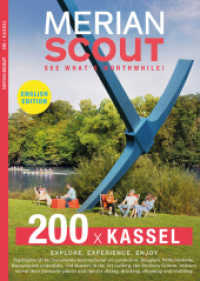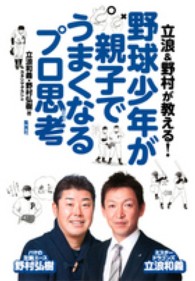出版社内容情報
文化が衰弱していると感じられるのはなぜか.情報化・消費化が進む中,思想性に着目して,詩歌・小説の歩みを検証.尊重一辺倒の態度を排し,伝統を「大胆な自己革新を行う運動体」と位置づけて,芸術・社会の再生を問う.
内容説明
日本の文化が衰弱していると感じられるのはなぜか。教育改革論議で典型的に見られる「伝統尊重」の狙いは何か。情報化・消費化の進行を把え返しながら、詩歌・小説の歩みを思想性に着目して検証。伝統を「大胆な自己革新を行う運動体」「新しい文化芸術を形成する源」と位置づけて、混迷する時代における芸術・社会の再生を問う。
目次
第1章 文学の衰弱(熱気を失った現代文学;詩のもつ位置と現在―短歌・俳句への批判と反批判 ほか)
第2章 衰弱の原因(統計から文化状況が見えるか;高度成長・技術革新―第一の理由 ほか)
第3章 日本文化の伝統とは何か(伝統論を避けた印象批評、事大主義;論じられるべき伝統 ほか)
第4章 伝統の継承(文学の危機への対応;“歌”は聴こえるか? ほか)
著者等紹介
辻井喬[ツジイタカシ]
1927年東京に生まれる。1951年東京大学経済学部卒業。詩集『不確かな朝』を1955年に出版以来、数多くの作品を発表。現在、詩人、小説家。セゾン文化財団理事長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Nobu A
9
辻井喬著書初読。そもそも本書はどんな経緯で入手したのかが最初の疑問。積読本を溜め込むものじゃない。創造力に関する源が理解出来ればぐらいの安直な思惑だったかも。読了後、著者をググって思い出した。本名はあの有名な実業家、堤清二。何かの本で言及があり購入したのを思い出す。質実剛健な文体。学者並みの文才と論考。詩を嚆矢とする文学の歴史。統計的には我が国の文化は衰退しているとは言えないが、自由市場経済下、純文学とエンターテイメントの垣根がなくなり、環境の悪化が作家と読者、両者とも創造力の低下に繋がっているのは得心。2024/08/16
ceskepivo
9
日本芸術・文化の再生を考える上で、もっと読まれるべき本だ。「何事も経済発展に貢献するかしないかで判断する社会を作っておいて、教育基本法を変え、道徳教育を要求し、「教育の原点は家庭であることを自覚する」べし、と主張する精神の構造の正当性を疑いたくなるのは私ばかりではないはずである」との指摘は鋭い。2015/10/10
比丘尼坂
2
20年前に出版され、日本が壊れてきていると言われる今、読むべき本。文化・芸術のことを言っているように思えるが、著者はこれらを引き合いにして、明治以降の近代日本を批評している。文学的で難解な言い回し、詩・和歌・短歌等への関心や知識があればなお理解が深まると思うが、1回読んだだけでは完全な理解はできなかった。しかし、著者の近代日本思想の分析は納得と共感ができた。但し、分析と更なる問題提起に終わっている。あとがきから読めば、著者の問題意識が分かり理解が深ると思うが、反面、著者の考えにひきこまれるかもしれない。2020/05/10
norio sasada
1
https://blog.goo.ne.jp/sasada/e/38a385ecf8dcba42989fd65877d2e86b https://note.com/norio0923/n/n71399ba28bf62007/02/09
takao
1
うーん2017/01/20