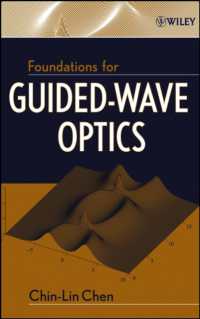出版社内容情報
古来,人びとは労働をただ「生活のための労苦」とだけ考えてきたわけではない.自然や超越者とのかかわりで,さまざまに意味づけて働いてきた.本書は,主要な労働観の系譜をたどり,その流れの中から,哲学的宗教的な見方をこえた科学的労働理論がいかに形づくられてきたかを明らかにし,その思想的遺産が今日にもつ意味を考える.
内容説明
古来、人びとは労働をただ「生活のための労苦」とだけ考えてきたわけではない。自然や超越者とのかかわりで、さまざまに意味づけて働いてきた。本書は、主要な労働観の系譜をたどり、その流れの中から、哲学的宗教的な見方をこえた科学的労働理論がいかに形づくられてきたかを明らかにし、その思想的遺産が今日にもつ意味を考える。
目次
序 人間にとって労働とは
1 労働観の系譜
2 社会的労働の理論
3 人間疎外と労働
4 現代社会と働くことの意味
結び 補論的対話
著者等紹介
清水正徳[シミズマサノリ]
1921‐2004年。専攻は哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
23
どうも古本屋から調達した感じがする。若干の薄い赤鉛筆を引用。労働:人間が自分と自然との物質代謝(Stoffwechsel)を自分自身の行為によって媒介し、規制し、制御するような人間と自然との一過程である(20頁)。本書を通じて、如何に、多くのものからの疎外が社会的に起きているのか、 愕然とさせられる。こうした各種疎外からどう救済されるべきなのか? 現代の読者にも鋭く問われることが多いと思う。2015/05/25
yuji
10
55歳になって働くことの意味を若い時とは違う感覚で問い直している。本書で疎外と物神性という概念を知った。人間は自然の一部で本能的に生きるための労働が、誰かのため特に資本家の貨幣増大のための労働に取り込まれ労働から疎外された。労働を商品化し労働に取り込まれため。人間が生み出す商品にもかかわらず商品そのものに神秘性を見る。その究極が貨幣。貨幣はあらゆる商品と交換できる。西洋では労働が罰なので定年延長に対してデモがある。早く労働から解放されたい。労働の価値が本能と乖離するほど解放されたい気持ちはよくわかる。2025/08/31
まさげ
9
一度読んだだけでは理解できない内容でした。 西洋と東洋の労働観の違いは面白かったです。2025/03/30
オザマチ
8
プロテスタントの思想や資本主義の考え方も盛り込んで…が、通しで理解するのは自分には難しかった。2015/09/06
ゆき (Kou)
5
労働思想の系譜を辿る内容で、題から啓発的な内容と予想するといい意味で裏切られる。ヘーゲル・マルクスの「疎外」を骨子に据えた内容。難解な概念だが、意味の変遷も含めて、丁寧に説明されていてとても勉強になった。資本主義の発展により労働の分業化が促進され、労働はさらに細切れとなる。さらに、本来は労働者へ還元されるべき労働が、資本へと吸収されることで労働は年々耐え難いものと化してきている。この「支配する労働」が疎外の本質だ。 これに対する問題意識は当然であるがその対処の結果がソ連やユーゴスラビアというのは残念↓2016/05/25
-

- 電子書籍
- イケメン社長に憑依されました【タテヨミ…
-
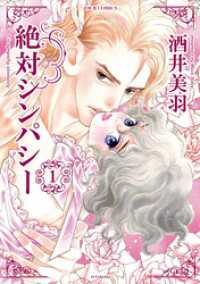
- 電子書籍
- 絶対シンパシー 1 ジュールコミックス