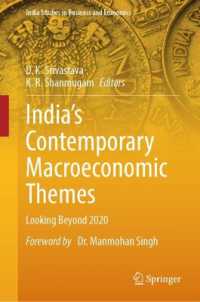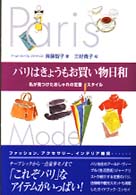出版社内容情報
民主主義という言葉はかつての輝きを失なってしまった感が強い.しかしそれは,体制の違いを問わず最高の価値を付与されていることに変わりはない.本書は,近代民主主義の歴史を克明にたどりつつ,その理想と現実との対抗関係を明確にし,さらに現代政治を構成する原理としての民主主義を浮き彫りにして,新たな展望を拓く.
内容説明
民主主義という言葉はかつての輝きを失なってしまった感が強い。しかしそれは、体制の違いを問わず最高の価値を付与されていることに変わりはない。本書は、近代民主主義の歴史を克明に辿りつつ、その理想と現実との対抗関係を明確にし、さらに現代政治を構成する原理としての民主主義を浮き彫りにして、新たな展望を拓く。
目次
序章 現代史のなかの民主主義(期待と幻滅;ワイマールの悲劇 ほか)
第1章 民主主義の歴史(前史としての古典古代;革命の炎 ほか)
第2章 民主主義の理論(民主主義の価値原理;民主主義の機構原理 ほか)
第3章 現代の民主主義(民主化と大衆化;管理者国家と民主主義 ほか)
終章 民主主義の展望のために(歴史的展望への要求;国家の問題 ほか)
著者等紹介
福田歓一[フクダカンイチ]
1923年神戸市に生まれる。1947年東京大学法学部卒業。専攻は政治学史。東京大学名誉教授、明治学院大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
10
「民主主義という言葉がもはや積極的な原理としての意味を失いますと横行するのは、その消極的な用法であります。つまり共産主義に反対するから民主主義だ。帝国主義に反対するから民主主義だという珍奇な主張でありまして、冷戦時代には少しも珍しいことではなかった。お隣の韓国には、まだそういう用法が残っております。こういう消極的な用法が支配的になりますと、反共とか、反帝でさえあればいいのですから、政治の保守化は必至であります」2018/04/18
まさにい
9
深い。この本、学生時代に読んでおきたかった(もう40年近く前のことだが)。ただ、この本を読み解くには世界史や思想史の知識が前提となるのだろう。そうだとすると、今読んで初めて解る本だったのだなぁと感じもする。民主主義に伴う無力感についての問題は、現在にも通じる。今度は、線を引きながら、再読を近いうちにしようと思う。本来複雑な事象を理を持って解決しなければならないのに、情緒や情動をもって貫き通そうとする傾向に対してこの当時から警鐘を鳴らしている点はさすがとしか言いようがない。2018/10/16
シノウ
8
古代からの民主主義の変遷をコンパクトにまとめた書籍。 アメリカ式のゼロから生まれた民主主義と、イギリスなどヨーロッパの流れを汲む立憲主義から変質した民主主義の違いが描かれている。 民主主義の展望を述べる章において国民国家を「絶対王政が強権で作り上げたこの単位にどうやらガタがきている」という慧眼はお見事である。2020/10/07
スズツキ
6
民主主義の光と影をまとめた新書。『英国における労働者階級の状態』をはじめ、恒産も教養もない人間にまで選挙権を付与することへの問題性。フランスの民主主義が制度化されたのは第三共和政憲法が制定された1875年以後だが、もともとネガティブに残った秩序としてだった……等々、日頃皆の唱える平和の象徴としての民主主義に疑問を呈する格好。トクヴィルの説く民主主義の世界において自由を育てていくには「宗教、教育、自発的結社」が必要という項目が印象に残る。2014/04/07
ぬにぇ
5
書かれている内容は基本的に民主主義論における基礎的な内容で、素晴らしく新しい発見があるわけではないかもしれない。しかし、この本のおかげで民主主義・自由主義・立憲主義・議会制というそれぞれ異なる制度、運動、主張がどのような過程で融合していったかを再確認できた。またアメリカ民主制の発展やイギリスにおけるそれが詳しく説明されているのもありがたい。 大衆社会の進展による民主主義の難しさ(ポピュリズム、政治への無関心)はこれほど前から指摘され、解決の模索がされているのか… 次は自由主義関連の本も読みたい。2024/10/22
-

- 電子書籍
- 思春期の子をもつお母さんへ - 揺れる…