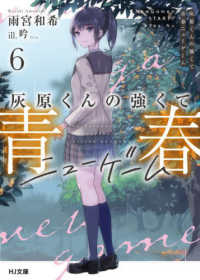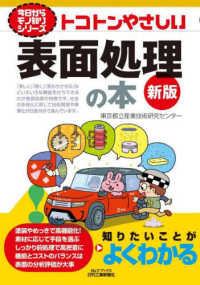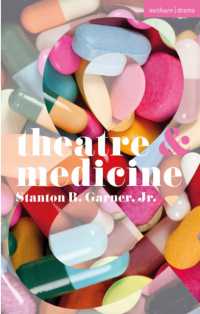出版社内容情報
野生時代のものとは全く違った存在となってしまった今日のムギやイネは,私たちの祖先の手で何千年もかかって改良に改良を重ねられてきた.イネをはじめ,ムギ,イモ,バナナ,雑穀,マメ,茶など人間生活と切り離すことのできない栽培植物の起源を追求して,アジアの奥地やヒマラヤ地域,南太平洋の全域を探査した貴重な記録.
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さきん
27
日本はどうしても稲作がクローズアップされがちだが、大豆や大麦、小麦、トウモロコシ、雑穀の伝播や地域別の特色も捉えて初めて農耕のおぼろげな一角が見えてくる。アフリカや南米にはまだ日本では知られていない雑穀がたくさんあるそうで、実際に見て食べたい気持ちが膨らんだ。日本は照葉樹林文化として分類され、麹菌を使った酒造りや葛餅などに特徴が見いだされる。ポリネシアの根菜文化は簡単に栄養が取れる、一方で地中海気候文化は工夫が必要との点で近代化への条件は西欧の方が優位に働くという説明で笑った。2021/06/17
TCD NOK
16
食に対しての信仰など、当時の人々の精神的な考察はあえてせず、余計なものを削って栽培そのものが文化であると明記。なのでページ数は200にも満たないのだが、その分次々に感心することが飛び込んできた。宮崎駿がこの本に感銘を受けたというけど、ここから新たな創作に繋げるのがすごい。自分はただ感心しただけど。2019/07/08
ヒナコ
14
作物として栽培されている植物は、人間が長い時間をかけて品種改良したものである。本書では、それらの植物の起源と、地球上の諸地域における農耕文化との関りや、それぞれの農耕文化のもとに開発された芋や麦や雑穀などが、どのように伝播していったのかが考察されている。 本書の初出は1966年と古く、最新の議論では本書が提出している説が受け入れられているのか私には全く分からないが、雑穀がアフリカで品種改良されていき、それがペルシアや中国を経て、水田で栽培される日本の稲になっていったというのは、興味深い議論だった。→ 2022/10/15
fseigojp
13
陸稲が水稲になったという今では怪しい言説もあるが、照葉樹林文化という偉大な学説のもとになった記念すべき本2015/07/24
斑入り山吹
12
こんなに凄い本がわたしの生まれるまえに出ていたなんて!ジャレド・ダイアモンドを読んでふんふんと思ったことは、こちらの本にずいぶん載っていた。読む順番、逆でしょ。新大陸から来た野菜、って気にはしていたけど、遠く古くアフリカから来た野菜、って意識していなかったなぁ。種の撒き方/苗の植え方、栽培方法とセットの考え方が面白い。山岳地帯の人々は好んでそこに住んでいる、っていうのが腑に落ちた。山村に移住して20年、ネイティブと話していてなんとなく思っていたことだから。ピリッとユーモアのきいた文章も楽しい。大した本だ。2013/08/28
-

- 和書
- 電磁波回路