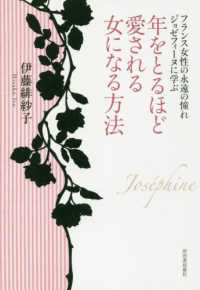出版社内容情報
ケンブリッジ,オックスフォードの両大学は,英国型紳士修業と結びついて世界的に有名だが,あまり知られていないその前過程のパブリック・スクールこそ,イギリス人の性格形成に基本的な重要性をもっている.若き日をそこに学んだ著者は,自由の精神が厳格な規律の中で見事に育まれてゆく教育システムを,体験を通して興味深く描く.
内容説明
ケンブリッジ、オックスフォードの両大学は、英国型紳士修業と結びついて世界的に有名だが、あまり知られていないその前過程のパブリック・スクールこそ、イギリス人の性格形成に基本的な重要性をもっている。若き日をそこに学んだ著者は、自由の精神が厳格な規律の中で見事に育くまれてゆく教育システムを、体験を通して興味深く描く。
目次
パブリック・スクールの本質と起源
その制度
その生活(寮;校長;ハウスマスターと教員;学課;運動競技)
スポーツマンシップということ
著者等紹介
池田潔[イケダキヨシ]
1903‐1990年。リース・スクール卒業、ケムブリッヂ大学卒業、ハイデルベルグ大学に在学した。専攻は英文学、英語学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新地学@児童書病発動中
113
名著と評価の高い岩波新書。著者が経験したパブリック・スクールの生活が格調高い文章で描かれている。かなり昔の本なので、この本を読んで現在の英国の教育が分かるわけではない。一つのエッセイとして読めば、楽しめると思う。著者が初めてキングス・カレッジの礼拝堂の鐘が鳴る音を聴いた時の感動や、英会話の特訓をした教師がレッスンが終わったときに見せる優しさなど、感動的なエピーソドが多く含まれている。この本のテーマである、自分を厳しく律することで真の自由を手にできる、と言う英国流の処世術はどんな人にとっても大切だ。2015/01/24
KAZOO
103
何度目かの再読です。日本の社会が変な方向に向かいつつあるときに時たま読み返しています。大衆迎合主義的な日本ではこのような教育というのは無理なのでしょう。オックスフォード、ケンブリッジといった大学の教育を考えると本当にいい意味でのエリート教育というものがある気がします。ゆとりと歴史を重んじている気がします。2015/10/19
佐島楓
42
戦前から戦後直後にかけてのイギリスのパブリックスクールの生活について書いたもの。現在どうかということについてはあまりわからないものの、伝統を重んじるイギリス、あまり変わっていないものと思われる。版を重ね読み継がれる本。2015/08/06
獺祭魚の食客@鯨鯢
39
大学進学率が50%を超えている。戦後の受験戦争による教育熱中時代は高度経済成長時代と重なっている。質より量とばかり大量の「ホワイトカラー」の企業戦士がマンモス大学から送り出された。 知的好奇心や向学心があまりない「学士」には詰込み勉強のほろ苦い思い出が残った。 偏差値による全ての生徒の序列化は東大理三を頂点とする受験カーストとなった。出身大学によるレッテルは人格にまで及ぶ。東大卒業生全てが「ノブレスオブリージュ」を身につけているとは限らない。むしろ東大生なのにという十字架を背負うことでもある。2021/05/23
みねね
35
新たなボスが、式辞の中でパブリック・スクールの逸話を挙げられた。「水をやりなさい。ローラーをかけなさい。」袖で聞いていた僕は、なけなしの検索力でこの本に辿り着いた。 教育者の端くれとしてはもちろん、海外古典に手を出し始めた身として、本書から得るものは大きかった。 ホールデンよ、フィリップよ、君らが体制の歪みに挟まれて勇退を余儀なくされたように、厳しい規律は欠陥だらけだ。しかし自由の拡大解釈が進んだ今日の「誰一人取り残さない教育」、あれはつまるところ誰一人掬い上げない教育である気がするのは僕だけだろうか。2023/04/20
-
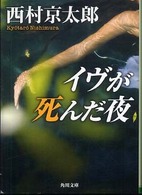
- 和書
- イヴが死んだ夜 角川文庫