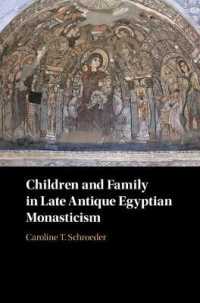内容説明
なぜある国では民主主義が成立し、他ではファシズムや共産主義革命が招来されたのか。近代化の異なる道筋を、社会経済構造の差に注目して説明した比較近代化研究の名著。下巻では、日本とインドを分析し、理論的考察を展開する。
目次
第2部 近代世界に向かうアジアの三つの道(承前)(アジアのファシズム―日本;アジアにおけるデモクラシー―インドとその平和的変革の代償)
第3部 理論的意味と客観化(近代社会への民主的径路;上からの革命とファシズム;農民層と革命;反動的思想と革命的思想;統計と保守的歴史叙述についての覚書)
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
113
下巻も読むのに時間がかかりました。この巻には日本とインドの例を示していて、前者ではアジアのファシズム、後者でデモクラシーについて論じています。ただ若干不満なのは西欧に比較して日本の場合は上からの革命のためにファシズムを育てやすい土壌があったということを述べられています。上からの革命というよりも、ある意味平等性(能力のあるものが力を持つという)があった軍部によるリーダーシップが農民層(当時としては労働者よりも割合が大きい)の支持を受けたということがわたしは大きいと感じました。2019/08/13
ステビア
21
封建的特権階級・ブルジョワ・農民の力関係によって近代化の様相が決まり、ブルジョワ階級の生成が進まないと資本主義的デモクラシー社会には行きつかないということかなぁ。講座派と同じ問題意識。解説が的確に内容を要約しているので、そこだけでも読む価値がある。2022/08/28
Hiroshi
7
下巻は日本とインドを分析してからまとめていく。江戸時代が始まった頃はほぼ農民は自作農だった。だが飢饉などで田畑を売り払う者が出てきて、本百姓に対し水呑百姓や名子・譜代・下人という土地を持たない農民もいた。農民が地主となり富裕層ができた。明治になると地租改正で土地所有者が納税者となった。その後も松方デフレや大恐慌で農地を手放す者が出て、終戦時には農民の約半分が小作農であった。明治維新は武士同士の勢力争いであり、階級革命ではない。英仏米の革命とは余りに違う。民主主義・資本主義の一部を取り入れたに過ぎないのだ。2024/08/26
politics
4
下巻では日本・インドの事例、まとめが収められている。日本はドイツと同様に上からの変革からファシズムに至ったとの図式で描かれているが興味深い記述も多くある。本書ではインドの事例研究が一番の目玉になるのだろう。第3章はこれまでまとめになっており、議論の整理には役立つしドイツ等の事例は挿入されているので大変興味深かった。小川氏の解説にあるように古さはあるものの、博物館展示よりはこれからも読まれる古典であることには変わりないだろう。2021/06/20
しゅん
2
下巻は日本とインド。日本は多少わかりやすいかと思ったがそうでもなく、苦労する。自身の歴史知識の足りなさが情けなくなる。ただ、社会における力学が革命など、社会を動かすということの意味が、なんとなくわかってきた気がした。2020/01/20
-
![魔法使い様の愛し方[1話売り] story05 ××LaLa](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1311316.jpg)
- 電子書籍
- 魔法使い様の愛し方[1話売り] sto…