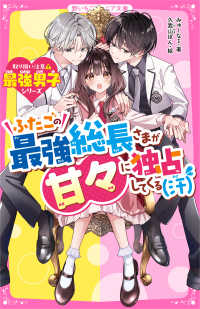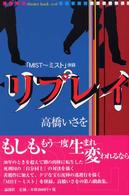出版社内容情報
種々の祭儀のあったイスラエル社会の中で,寄留者層にすぎない特殊なレビびと祭司が影響力のある地位を獲得し,祭司としての魂のみとりの活動を通じて倫理的な教え(トーラー)を作っていった過程と,ヤハウェ主義的に敬虔で高貴な平信徒知識層が,イスラエルの宗教文化の知的創造の発展に担った役割について分析する.
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
逆丸カツハ
34
すごい宗教だなと思う。激情的というか…。昔大学の講義でどこか憂いた様子で旧約聖書の解説をする先生がいたのだが、その立ち振舞いの理由がわかったような気がする。2025/08/15
うえ
9
「イスラエルの宗教性は、エジプトのそれに対してとは異なって、バビロニアやフェニキアの公式の宗教性に対しては、一つの重要な点で親近性をもちつづけていた。それはすなわち彼岸の無視、ならびにそれと結びついていた諸々の思弁の無視である。しかしながら別してバビロニア的な諸々の神観念、すなわちシンクレティズム、神々の万神廟、すべての神々を主神の「現象諸形態」として主神のなかに吸収してしまう単一神教、太陽神のつねに優越する位置、これらは…イスラエルの神観念にとっては未知のものにとどまった。」2025/07/05
Akiro OUED
3
ヤハウェは、善悪の両方とも行うという際立った特徴を持つ。善行は神、悪行は悪魔、という役割分担しない。面白い。全ては自分の行いの結果というベドウィン魂がそんな神を仕立てたのか。社会的連帯責任より個人の自己責任を優先する社会では、ヤハウェのようなポピュリストが台頭しやすいのかも。2023/07/02
壱萬参仟縁
3
ベリース(契約)思想は、いっさいの神の意志の探究を駆り立てて、少なくとも比較的に 合理的な(傍点) 問題提起とその解答の合理的手段との方向へとおもむかしめた(419ページ)。上巻の提起を更に深めて考察している箇所。プレイボーイの人には「結婚いがいの関係での男の性交を禁止することは、ずっとのちの捕囚期にようやく始まった」(474ページ)とのこと。本著からすれば、日本女性は貞節(操)だが、これは違和感。貧者や病人へのカリテートの保護(634ページ)。弱者への保護をどうすべきか。政治家や官僚も本著で学習を願う。2012/12/19
rynly
2
滅亡や捕囚といった禍や苦難の意味づけが、「自民族に復讐する神」という解釈によって為され、しかもそれが平民層にまで浸透したことをヴェーバーは驚嘆しつつ繰り返し強調する。古代イスラエルにおけるこの「空前の歴史的パラドクシー」こそが、西欧文化世界を特徴づける「世界の脱魔術化」の出発点であるという認識。2014/04/01
-

- 和書
- もういちど会える日まで