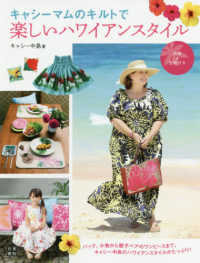出版社内容情報
成熟した資本主義の複雑なメカニズムを分析した書物として,本書はケインズの『一般理論』と並ぶ古典的地位を占める.資本主義経済過程を循環‐発展の二段階的に把握し,革新・新結合という経済内部の自発的な発展力に着目し,信用・資本・利子・利潤・景気循環などの問題を統一的に解明する.
目次
第4章 企業者利潤あるいは余剰価値
第5章 資本利子
第6章 景気の回転
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
加納恭史
19
下巻まで読み進むと反って理解し易くなる。訳者あとがきは上巻のまとめとこの下巻への橋渡しが分かり易い。第二章の「新しい結合」は新機軸イノベーションのことであった。この新機軸は新しい生産、新しい販路、新しい発見など経済発展の核心となっている。原書の根幹は第一次世界大戦前に構想された。シュンペーターになじみの深かったアメリカ合衆国は旧い慣行などの制約もなく、ほぼ自由自在に経済の舞台に参入し得たし、退場もできた。新しい類いの経済人たる「企業家」の活動こそが、経済発展の根本動因となっている。下巻は企業家利潤から。2022/07/09
えちぜんや よーた
10
スマソ。(下)はほとんど読んでません(上)のレビューを見てもらえれば幸いです。全文をよどみなく読める人はすごいと思います。2012/08/12
Francis
9
10数年ぶりの再読。下巻は企業車利潤、資本利子、景気の回転を扱う。利子がどうしてあるのか、また、どうして好況・不況は起こるのか、ケインズとは異なる視点から語られる。資本主義がなぜこれほどの発展を見せたのか、ひとつの回答を与えてくれる。ケインズ「一般理論」と同様に、難解ながらも経済理論を理解する上では欠かせない名著。2015/02/09
isao_key
9
下巻は企業者利潤あるいは余剰価値、資本利子、景気の回転の3章から構成されている。中でも資本利子について詳しく書かれている。この中で利子について、他の事情が同一ならばと断り書きを入れた上で「利子は企業者利潤とともに高騰する企業者利潤こそ利子の源泉であり、この源泉の変動は購買力に対する需要の増減という媒介を通じて、同方向の利子の変動を直接に惹き起こすのである」とある。また好況の利得と不況の損失に関しては、無意味、無機能ではなく、経済発展のメカニズムにおいて排除することのできない本質的な要素として捕らえている。2013/12/30
富士さん
7
経済学の前提を共有できていないので、利子論はまったく理解できませんでしたが、経済動態のマクロな議論はわかったような、気がしなくもない。競争を重ねて独占に至っても、同じ商品だと限界効用が低下することで取れる利幅が減り、値段は原価に近づくので独り勝ちの意味は薄く、マルクスが言うようにはならない。起業家がもたらす新しいものこそ高い付加価値をつけることができ、経済全体を発展させることができる。新しいものは大きな利益を期待させ、投資を活発化して好景気をもたらすが、あらかた行き届くと不景気に転じる。そんなところかな。2025/01/12