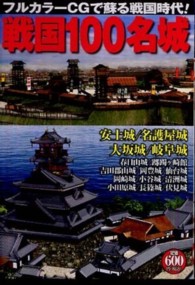出版社内容情報
ドイツ神秘主義の源泉エックハルト(一二六〇頃‐一三二八?)の説教二十二篇と論述一篇ほかを収録.説教の中心は心の自由と平安の問題であり,苦しみや悲しみのただ中にあってもなおそれを高く超え出た在り方のあることが「離脱」の概念を介して説かれる.ユングはエックハルトを評して「自由な精神の木に咲く最も美わしき花」だといった.
内容説明
ドイツ神秘主義の源泉エックハルトの説教22篇と論述1篇ほかを収録。説教の中心は心の自由と平安の問題であり、苦しみや悲しみのただ中にあってもなおそれを高く超え出た在り方のあることが「離脱」の概念を介して説かれる。
目次
説教(魂という神殿について;魂の内にあるひとつの力について ほか)
論述(離脱について)
伝説(マイスター・エックハルトと交わした、善き修道女の善き会話;善き朝について ほか)
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新地学@児童書病発動中
122
離脱という概念を通して神と一つになることが説かれる。離脱とは自分自身を捨て去ることで、最終的には自分自身を捨て去ったという心さえも捨て去ることが求められる。徹底的に無を目指すのがエックハルトの思想の特徴で、禅などの東洋の宗教と共通点がある。彼は異端の烙印を押されたが、それは彼の思想がラディカル過ぎたためだろう。しかし、エックハルトの思想の中心には十字架の上で、苦しみながら死んでいったイエスに対する深い信仰が横たわっていると思う。神が苦しむのがキリスト教の神髄でそれを最もよく理解していた信仰者だった。2016/03/13
新田新一
40
この本は10回以上読んで、影響を受けました。エックハルトはドイツの宗教者です。苦しむことに大きな意味があると主張し、苦しみの中にありながら、離脱を目指す生き方が説かれています。キリスト者なので、キリストへの深い信仰がエックハルトの思想の中心です。と言っても教条主義的なものではなく、神のために神を捨てることが求められる純粋さがあります。生きている限り人間は苦しみから逃れることはできません。その苦しみを一番理解していたのは、十字架上のイエスです。苦しみの中でイエスが共にいると思うことは、私にとっては→2025/08/30
yutaro sata
32
最初はこの「説教」という語りの形式に馴染めず文が頭に入ってこなかったのだが、その語りに身を委ねているうち、これは「行」的、あるいは他力的な話だぞ、と思えて、急に話が身近に感じられるようになってきた。内側を無にしなければ神の入る隙間がない。何も意思していない境地こそ至高である。何も求めていないということを、認識すらしてはいけない、など、なんだか名人論的、達人論的ではないか。2023/02/28
松本直哉
31
薔薇という名前でなくても、薔薇の香りは変らない。名前を捨てて薔薇と向き合うように、自分の名前・属性・偶有性を捨てても残るもの、からっぽの自分、その中に、神は流れ入る。神にも名前はない。名付けられないもの、どのような述語でも表せないもの、それとの合一。そこではいっさいの言葉は消え、無媒介で神と自分は溶け合う。教義も教会も必要なく、ただ自分と神のみがある。神との合一は、自分が神になることではなく、川の水が海に溶け込むようにして、神のなかに自分が溶解することだと言えるだろうか。2020/05/29
マウリツィウス
25
【《神秘主義とエックハルト》】《神秘主義合一との課題》、《古典思想と現代思想》、《『潔白』、「この条件を創造する為」に必要な主題、『贖罪と媒介』、「『罪』の思想は『虚構』を放棄することで産出される」、「よって『現代思想』と『罪』の課題を再び求める」》。《「罪の配置とその認識」》、《この先にあるもの》、《『ヒト』は「造り変わること」が出来る》、《造形と様式》、《表情ではなく「葛藤」か》。《『葛藤』を「覚えること」、「これが『象徴と真実』となるか」》。「《葛藤は成長の糧》」、《この奥義は先を結んでいく》。/始2015/03/19
-

- 和書
- 水辺空間の魅力と創造