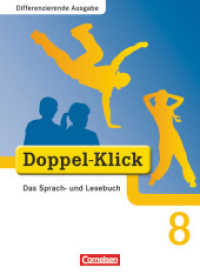出版社内容情報
ニーチェの処女作.ギリシャ文化の明朗さや力強さの底に「強さのペシミズム」を見たニーチェは,ギリシャ悲劇の成立とその盛衰を,アポロ的とディオニュソス的という対立概念によって説く.そしてワーグナーの楽劇を現代ドイツ都市の復興,「悲劇の再生」として謳歌した.ここには倫理の世界を超えた詩人の顔が見てとれる.
内容説明
ニーチェ(1844‐1900)の処女作。ギリシャ文明の明朗さや力強さの底に「強さのペシミズム」を見たニーチェは、ギリシャ悲劇の成立とその盛衰を、アポロ的とディオニュソス的という対立概念によって説いた。そしてワーグナーの楽劇を、現代ドイツ精神の復興、「悲劇の再生」として謳歌する。この書でニーチェは、早くも論理の世界を超えた詩人の顔をのぞかせる。
目次
アポロ的夢幻とディオニュソス的陶酔
ディオニュソス的ギリシア人
アポロ的文化の基底
アポロ的・ディオニュソス的なギリシア文化の推移
抒情詩人の解釈
詩と音楽との関係
悲劇合唱団の起源
サチュロスと演劇の根源現象
ソフォクレスとアイスキュロス
悲劇の秘教〔ほか〕
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
syaori
71
「生存と世界は美的現象としてのみ是認される」ことを謳う処女作。作者は近代の、いつ死ぬとも知れぬ生の不条理から目を逸らし科学によって地上の幸福を手にできると信じる楽天主義を嗤い、ギリシア悲劇を「この生存とは違った存在」を示すものだとします。悲劇は、矛盾に満ちた根源的生を示すディオニュソス的なものと、それを夢幻的・芸術的仮象で包むアポロ的なものが止揚し合い、「発生した以上は、苦悩にみちた没落を覚悟しなければならぬ」という生の苦痛を陶酔と共に是認させるもので、ツァラトゥストラの高貴な没落の端緒を見るようでした。2021/10/18
みつ
29
学生時代以来だから40数年ぶりの再読。今回読んだのは図書館にあった白水社の『ニーチェ全集 第1巻』(浅井真男訳、1979年発行)から。検索できなかったのでこちらに登録。「アポロン的」「ディオニュソス的」という対比的な用語以外、ギリシア悲劇の成立を述べた本であることすらきれいさっぱり忘れていた。ニーチェによればふたつの概念は前者が「夢」で個別的な世界、叙事詩、造形芸術に代表され、後者が「陶酔」で普遍的世界、抒情詩、音楽芸術に代表されるとしたうえで、ギリシア悲劇ではまず合唱団(コロス)のみがあったと説く。➡️2024/08/02
松本直哉
28
デルポイ(その語源は子宮)は世界のへそと考えられ、もともと女性神が支配する場所だったのを、アポロが横取りした(巫女たちは奴隷化された)経緯を見れば、アポロは女性性を抑圧する神。それに対して、ディオニュソス側の主役は、陶酔と熱狂で踊り狂う信女たち(マイナデス)なのだから、ディオニュソスは女性性を解き放ち自由にする神と言えようか。男性による支配を疑いもしなかったギリシャ世界に、すべてを破壊する狂乱の信女たちが押し寄せたときの衝撃を想像してみたい。こんなことは本書のどこにも書いていないことなのだけれど。2022/05/23
呼戯人
18
ニーチェがまだロマンチックな芸術家形而上学に捉われていたころの作品だが、やはり素晴らしい作品だと思う。「存在はすべて美的現象としてのみ是認される」という美の追求がこれまでにないほど深いところまで追求されている。悲劇的世界観に対してソクラテス以後の理性主義が対立し、世界が本来持っている流動する生成変化を捉えられなくなっているという批判は、いずれプラトンやキリスト教をニヒリズムとして指弾する後年のニーチェを彷彿とさせる。2016/01/07
K
17
高校卒業してすぐくらいに読んで、最初の数ページで挫折した記憶がある。久々に、今度は最後まで読んでみて大枠は理解できた気がする。古代ギリシャにおける悲劇の誕生と死、そして19世紀ドイツにおける音楽(特にワーグナーであるけど)としての悲劇芸術の再生が語られる。アポロ的とディオニュソス的という(言葉として非常に惹かれるところがある)概念を軸に説明する。真の悲劇は両特徴の絡みあいなのであると。その他は、ソクラテス批判が目玉。2024/03/13
-
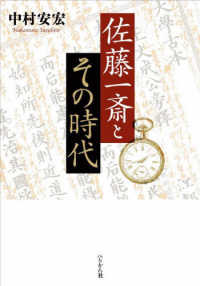
- 和書
- 佐藤一斎とその時代