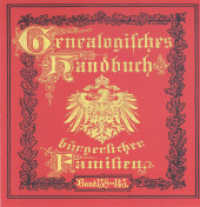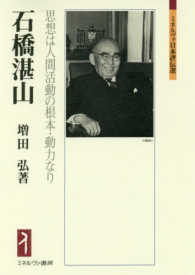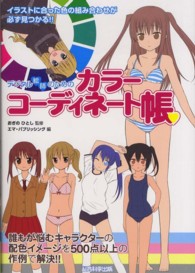出版社内容情報
東京大学の前身である南校で教鞭をとり,明治天皇に拝謁する機会をもったアメリカ人教師グリフィス(一八四三―一九二八)が,明治天皇の生涯をたどりながら,明治維新=日本の近代化が西欧の衝撃によるものではなく,日本人全体の力による歴史的必然であることをあとづけた書.特に天皇の日常生活を生々と描いた第三十章が興味ぶかい.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
isao_key
11
1915年に出版された本書は、明治天皇のみならず、日本が近代化へと進んでいる過程を外部者の目で書いている貴重な記録であるが、あまり読まれていないのが残念である。1870年末、福井藩主松永春嶽に招かれ、藩校明新館で教師をしたのち、1872年の始め明治政府に雇われ東京大学の前身である大学南校で理学や化学を教えた。1874年7月に帰国。最も印象的な記述は明治天皇の日常生活を書いた第29章と、御製歌16首を取り上げて解説している第30章である。明治天皇の夕食は普通は5品で、鶏のスープと焼き魚が大好物だったという。2016/07/27
1.3manen
8
1915年初出。著者は封建制を大名城中で見た唯一の外国人(340頁)。日本のミカドは生涯の日々をのらりくらりと過ごしていた(105頁)。ストレスフリーなミカドだな。民衆は外国の客人や交易には反対せず、交易を望みすらしていた(124頁)。日本の民衆が意外にも親外国人だと評価している(124頁)。The Japan Punchという石版刷漫画新聞の1874年12月号の漫画の事例が紹介されている(251-2頁)。日本人にとって詩歌は魂の鍛錬(302頁)。ニッポンでは刀が理想化されていた(309頁)。日本相対化。2013/04/04
にゃん吉
3
お雇い外国人だった著者が、明治天皇(ミカド)の生涯、ミカドの意義を中心に、日本について記述。日本を西洋化、近代化を進める優等生として、明治天皇をその中心にいる英邁な君主として称賛する視点で記述されており、興味深い。「「採用(アドプト)し、適用(アダプト)し、熟達(アデプト)する」ことは、特に日本的で、しかももっとも日本の名誉になる過程」とか、外部の目で的確に日本を見ていますが、キリスト教や西洋的礼式の受容を当然と考えているような記述もあり、良くも悪くも西洋優位の視点が貫かれています。 2019/05/25
新父帰る
3
著者は明治3年に来日、福井藩に呼ばれ、藩校で教鞭を執る。横井小南の甥の面倒を米国で看た縁。その後新政府に雇われ、東京大学で教鞭を執った。明治政府の業績を「ミカド」のそれとして、かなり赤裸々に描く。ペリー来航が、帝国の内乱を防いだという著者の論調は、岡倉天心も支持していると。また、お世話になった松平春岳をべた褒めしたのはやむ終えないか?著者は実際「ミカド」に何回か謁見していおり、ミカドのプライベートな生活まで詳細に記述している為に、日本語の翻訳は約60年後。本書は外国人が書いた唯一の明治天皇伝であると解説。2018/11/05
ウラー
3
東洋趣味とは異なる意味で日本が好きだという、明治期には希有な外国人による明治天皇論。堅苦しい天皇論ではないのがポイントで、明治天皇の好物なんかも書いてあったりして面白い。人物の評価が現代とかなり異なるのは、同時代に書かれたもの故だろうか2014/05/08