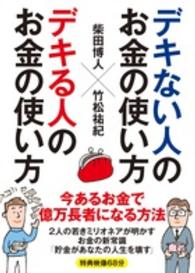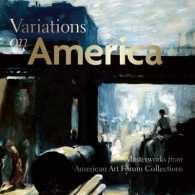出版社内容情報
インドでは古来ダルマ(法)とアルタ(実利)とカーマ(享楽)が人生の三大目的とされてきた.古代インドの名宰相カウティリヤの作と伝えられる本書は,アルタの立場から揺ぎない権力の確保のために王が採るべき権謀術数を説いたもの.これに比べれば『君主論』など「たわいないもの」だとヴェーバーは言った. (解説 原 実)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
20
能力は三種。 知識力は政策能力、国庫と軍隊力は権力、 勇武力は気力(48頁)。 敵を出し抜くには、 政策能力、権力、気力の順番で 優先する(177頁)。 巻末解説によると、 「王は臣下を財(ダーナ)と 名誉(マーナ)、即ち金と地位によって なだめすかし、人間の金銭欲・名誉欲 を巧みに見抜いて人心を収攬するが、 また他面必要とあれば残忍・非情な 術策を用いて世に害をなし、 また陰謀謀反を企てる不穏分子を 処罰することに躊躇してはならない」(444頁)。 2014/04/18
シンドバッド
9
下巻はいずれも面白い。 訳者の上村の日本語が素晴らしいことも奏功している。2015/12/16
isao_key
7
下巻は秘密の行動、外交政策、災禍、王の行動、戦闘、秘法、学術書の方法などが書かれている。解説で原實先生はカウティリアの考えで王とは、第一に自己の保身に最大の努力を払わねばならず、そのために各種の間諜を用いて常に人心の動きを掌握しなければならないとし、庶民は厳格な王を敬して遠ざけるが、王が寛大に過ぎると軽んずるから、君主たるものは時と場所に応じて硬軟両様の方策を使い分ける必要があるという。また欲望は悪人を助長したり、怒りは善人を抑圧する。多くの弊害をもたらすから、この両者はこの上ない悪徳とされる、とある。2014/11/14
みづはし
3
この本を読むまではインドという国には、「権謀術数」のイメージはありませんでした。しかし、本書で書かれている事は、古代中国を彷彿とさせる陰謀劇の数々。例えば、「反逆的な諸侯の息子に、「お前は実は王の子で、即位させてやりたいが諸侯の脅威のためにそれが出来ない」と言って、親である諸侯を殺すようそそのかし、その後でその息子も反逆罪として殺すべきだ」と言う話。それ以外にも民衆から税を巻き上げるために、ただの石像を神に見せかける方法が書かれていたり、目的のために手段を選ばない冷徹さがかいま見えます。2016/02/01
大ふへん者
2
古代インド、マウリヤ朝の宰相カウティリヤの書。マックス・ヴェーバーをして「これに比べればマキャベリの君主論なんぞ・・・」と言わしめた権謀術数ぶり。読んで納得です。安っぽいハウツー系処世術なんか捨てて、もうすぐ復刊するみたいなんでみなさん手に入れましょう。2013/11/03
-

- 和書
- 気管支喘息の診療