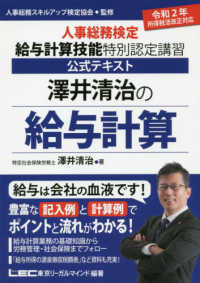出版社内容情報
『列子』八篇は『老子』や『荘子』とともに道家思想をつたえる代表的な中国古典であるが,「杞憂」「朝三暮四」「愚公移山」などよく知られた絶妙な寓言・寓話が多く,滋味ゆたかな説話文学の一大宝庫ともなっている.原文と訓読文に細緻な校・注を付し,さらに分りやすい現代語訳を加えた.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
14
原文→書き下し文→口語訳、後半は校・注、解題の順番。口語訳だけでも学習してみた。たえず生成したりたえず変化したりするものは、生成しない時とてはなく、変化しない時とてはない(24頁)。生生流転か。一生の四つの大きな変化とは、嬰児期、少壮期、老衰期、そして死亡期(39頁)。必ず勝つやり方を柔といい、必ず勝つとはいえないのを強という(114頁)。子貢は琴を奏でて歌をうたい、詩書礼楽の勉学に勤しみ、一生涯貫いたのは素晴らしい(167頁)。2013/08/27
まふ
13
筋道がはっきりしている。荘子が超感覚的であるとすれば、こちらはなるほどと納得し得る。一つ一つが起承転結のはっきりしたものである。天瑞、黄帝、周穆王、仲尼の各編であった。2001/01/11
roughfractus02
9
徳は外に現れるものではないのだから聖人は愚者のように見える。聖人は「木偶の坊(デクノボウ)」のようだと著者はいう。老荘思想を継承する本書は後世に老子の「道」、荘子の「遊」に続き「虚」をテーマとしたと伝えられる。全8篇中「天瑞」「黄帝」「周穆王」「仲尼」に「列子序」(張湛序) 「列子新書目録」(劉向序)を付した本巻は、孔子とその弟子や著者自身を主人公とした寓話で、「道」を体得し世界を「遊」ぶ「木偶の坊」たちがこの生を「虚」として生き、言葉では伝達できない実在へ超越する技芸を、様々な比喩を散りばめつつ伝える。2025/11/10
荒野の狼
4
登場人物は、孔子とその弟子(孔子が老荘思想を理解した人物として登場することが多い)、列子本人など。列子は、道を体得した人は木偶(でく)の坊(欺魄、泥人形)のように一見見えると解説する。それは、道を悟った人は無言だが、無言の沈黙を言論とするのもまた一種の言論(無言の言)である。ところが、真に道を体得した人は、かかる言・無言とかの区別をすべて相対的なものと見て、それらを超越している(p177)。この話は、宮沢賢治が雨ニモマケズの”デクノボウ”のようになりたいと叙述していることなどからも興味深い。2014/10/07
エヌ氏の部屋でノックの音が・・・
3
1987年 1月29日 初版2016/04/29