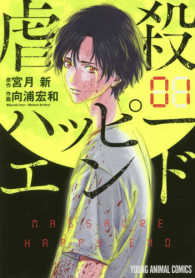出版社内容情報
暴力に対する嫌悪,人間の機械化に対する嫌悪,そして人間に対する愛を心に抱いて生きること――ユマニスムを生涯の思想とした著者(一九〇一―七五)の静かな祈願のことばは,読む者の胸に深い感動を呼び覚ます.真の知性の眼をもって人間性の根源を洞察するエッセイ・評論二十三篇を収録.(解題 清水 徹/解説 大江健三郎)
内容説明
暴力に対する嫌悪、人間の機械化に対する嫌悪、そして人間に対する愛を心に抱いて生きること―ユマニスムを生涯の思想とした著者(1901‐75)の静かな祈願のことばは、読む者の胸に深い感動を呼び覚ます。真の知性の眼をもって人間性の根源を洞察するエッセイ・評論23篇を収録。
目次
1(「テレームの僧院」のこと;やはり台所があったのか?;海に浮かぶ「テレームの僧院」について;「テレームの僧院」について(翻訳解説より)
「パンタグリュエリヨン草」について(翻訳解説より))
2(ユマニストのいやしさ;モンテーニュと人喰人;エラスミスムについて)
3(トーマス・マン『五つの証言』に寄せて;狂気について;文法学者も戦争を呪詛し得ることについて;人間が機械になることは避けられないものであろうか?;戯作者の精神;不幸について;宿命について;寛容は自らを守るために不寛容に対して不寛容になるべきか)
4(エドゥワール・シャンピヨンのこと;買書地獄;本を読みながら;一挿話)
5(アンリ四世の首の行方;白日夢 カトリーヌ・ド・メディチ太后の最期とその脚の行方)
6(老耄回顧)
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まふ
118
私の敬愛する故渡辺一夫氏の評論集。氏の暖かくかつ真摯な人間味あふれる評論と随筆が23篇ほど続く。専門領域であるラブレー、エラスムス、モンテーニュのルネサンス期ヒューマニズム(ユマニスム)の3巨人への思い入れはここでも十二分に伝わってくる。最も興味深かったのが最終章の「自伝」的随想。氏は韜晦の人であり、幅広く深く時に鋭い至言を遠慮がちにぼそりと語るその人格は少年、青年時代の自由な知的生活、きらめくような学生生活、さらには充実した教員、教授生活の過程でじっくりと生み出されたことがよくわかる。2024/04/23
lily
87
一生本を読んでいます宣言に毎日2冊読む決意表明の初日から挫折したりニヒリスト思想に希少価値を狙ったり愛書狂あるあるネタが満載でニンマリする。なんだって人間というものは、狂気なしにはいられぬものでもあるらしいからね。2019/07/18
esop
66
私はこういう行為に恐ろしい野蛮を認めて悲しむよりも、むしろ他人の罪を咎めながら自分たちの罪に対して、あまりにも盲目であるのを悲しむのだ/ヒューマニズムとは、人間の機械化から人間を擁護する人間の思想/寛容は自らを守るために不寛容に対して不寛容になるべきか/不寛容によって寛容を守ろうとする態度は、むしろ相手の不寛容を更にけわしくするだけであると、僕は考えている/現実性のない正義の空論は、現実の犯す罪禍に対する反省の糧になり、人類の進歩には欠くべからざるものでもある2024/05/17
奥澤啓
31
渡辺一夫。ラブレーを専門としたフランス文学研究の泰斗。日本のフランス文学研究を、初めて世界的水準まで高めたラブレーの翻訳と研究は日本の宝である。ユマ二スム思想を自身の在り方の根本とし、人間の本性を深く洞察する稀有の知性によって、平明な言葉で、静かに語られる文明観、人間観は永遠に古びることはないであろう。その人としての在り方、知性の在り方、平和を希求する精神は、加藤周一と大江健三郎に継承されたのを私は見る。大江健三郎は「思いこみの機械にならないように」という恩師の教えを、絶えず、胸底に秘めているという。 2015/01/05
獺祭魚の食客@鯨鯢
23
フランス思想の第一人者の随筆集です。大江健三郎氏や辻邦生氏の師としても有名です。 著者は「寛容」を無くし他者「不寛容」になること、即ち「攻撃」することは許されないとしています。何かに囚われ「狂気」に陥ること愚かさを指摘し、旧日本軍の暴走を批判しています。しかし、人文主義は教会至上主義へのアンチテーゼとしてギリシア思想のルネサンスとしてあくまでも白色人種至上主義的なスタンスであり、日本やイスラム、アフリカなどは寛容の対象としていないところに限界があるように思います。2018/07/15