内容説明
イスラーム神秘主義、仏教唯識論、空海密教、老荘思想、インド哲学、西洋思想の記号学を論じることで、人間の思考、存在を決定する「コトバの意味」の根源を探求する。意識の深層に拡がる、渾沌とした「言語アラヤ識」を措定し、東洋哲学の立場から言語哲学的に考察する。デリダの、井筒に応答した小論文を併載。
目次
1(人間存在の現代的状況と東洋哲学;文化と言語アラヤ識―異文化間対話の可能性をめぐって)
2(デリダのなかの「ユダヤ人」;「書く」―デリダのエクリチュール論に因んで)
3(シーア派イスラーム―シーア的殉教者意識の由来とその演劇性;スーフィズムと言語哲学;意味分節理論と空海―真言密教の言語哲学的可能性を探る;渾沌―無と有のあいだ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
96
井筒さんの「神秘哲学」に続いての若い頃の著作です。神秘哲学がギリシャの哲学についての論考であったのとは対照的にここでは東洋哲学について述べられています。東洋哲学といっても中国関連ではなく、やはりその後の専門となるイスラム関連が中心です。かなり難解な部分もありますが「人間存在の現代的状況と東洋哲学(講演録)」「シーア派イスラーム」「混沌ー無と有のあいだ」が比較的興味を持って読むことができました。2019/04/13
テツ
13
ぼくたちは日常的に森羅万象を言葉として表現し受容し、その対象を理解したつもりになっているけれど、決して言葉はその本質を表してはいない。どれだけの語彙を駆使しようが長文を積み重ねようが、言葉は目の前にある「それ」と完全に重なることがない。言語化は大切だ。どんな場合でも疎かにしてはいけない。でも言語化した「それ」も「これ」も、自らの内側に渦巻く感覚や感情、実相として正に目の前に存在する対象とは大きくかけ離れてしまうのだということも常に意識していなければならない。2023/01/19
CCC
12
カバー範囲広いなあ。個人的にはユダヤやイスラム絡みの話はまだついていける気がしたけれど、仏教が入るとよく分からなくなった。なぜか文化的距離が近いはずの話ほど難しく感じた。2019/06/13
兵士O
10
井筒先生の本は学術書の中でも、安いマルちゃん正麺ではなく、本格派の中華三昧のような感じです。最初は中国の老荘思想の後に、何でデリダが出てくるんだ?とちぐはぐなように思ったのですが、そもそも先生の構想の中に、伝統を重視するあまり埃をかぶっていた空海などの東洋思想を、当時の最先端だった記号学などと比較して、いい意味での「誤読」で新しい価値を見出すことが主眼にあるとあり、それで腑に落ちました。内容では、自分が絶対的存在と一体化する神秘主義の記述が多いような印象で、その時の先生のテンションが高いような気がします。2020/02/23
roughfractus02
9
前著で著者は東西の意識の「共時的構造化」を試みたが、本書では、東西各々に現れる「特殊問題」としてその構造の捉え方を検討する。意識の表層と深層をスーフィズムは「理性の領域」と「理性の向こうの領域」の二重性とし、デリダの著作では永遠の彷徨と終末論に執着するユダヤ性を生む砂漠に喩えられる。ウバニシャッドの「非有」、荘子の「混沌」は、光によって存在が明される以前の深層を表わすとされる。この意味の深み(深層)では生命は生きられず、自ら意味と秩序を作るしかない。その際生まれる分節化の「種子」を唯識派は阿頼耶識と呼ぶ。2021/01/16
-
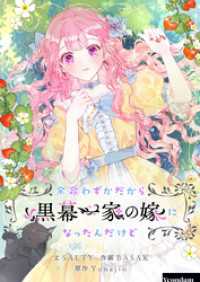
- 電子書籍
- 余命わずかだから黒幕一家の嫁になったん…
-
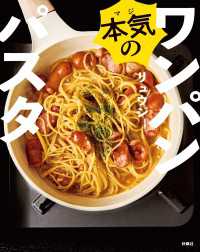
- 電子書籍
- 本気のワンパンパスタ 扶桑社BOOKS







