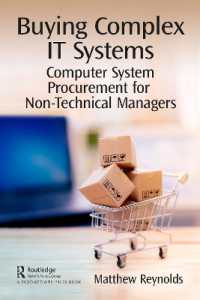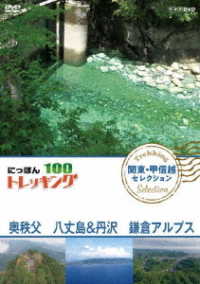出版社内容情報
真宗大谷派の僧侶となり,東京大学に学んだ清沢満之(1863-1903)は,親鸞の思想を哲学的に基礎づけ,仏教の危機的状況に立ち向って,明治期の精神界に大きな影響を与えた.本書は,結核に罹りながらも宗門改革運動に腐心した以降の文章を集める.晩年に深められた思索と信仰の言葉には,現代人の心に響く他力門思想の精髄がある.
内容説明
真宗大谷派の僧侶となり、東京大学に学んだ清沢満之(1863‐1903)は、親鸞の思想を哲学的に基礎づけ、仏教の危機的状況に立ち向かって、明治期の精神界に大きな影響を与えた。本書は、結核に罹りながらも宗門改革運動に腐心した時期以降の文章を集める。後半期に深められた思索と信仰の言葉には、現代人の心に響く他力門思想の精髄がある。
目次
第1部 他力の大道(親鸞聖人御誕生会に(他力の救済)
我は此の如く如来を信ず(我信念) ほか)
第2部 精神主義(精神主義;万物一体 ほか)
第3部 仏教の改革(教界時言発行の趣旨;大谷派宗教改革の方針如何 ほか)
第4部 信仰の諸相(仏教の効果は消極的なるか;他力信仰の発得 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
13
精神主義等の清沢満之のエッセンスを凝縮した一冊。絶対無限に対する考え方や真俗二諦と道徳の問題等、現在の問題に共通する所が多すぎて、一読ではとても理解しきれなかった。只々印象に残ったのは足場のしっかりした人間の強さと、転換期における危機感。両方とも現代人の指針になりそうなものばかりである。後読みながら内観というものが良く多用されることから原始仏教を想像したが、著者が阿含経に親しんでいたと解説に書いてあり何となく納得させられた。いずれ機会を見て再読したい一冊でありました。2012/07/22
isao_key
9
明治期の宗教思想・仏教運動家である清沢満之の論文を集めた論集。改題によると必ずしも清沢自身の手によるものではないものもあるというが、考え方、信条は伝わる。多くは雑誌『精神界』『教界時言』に発表した文章をとっている。仏教用語を駆使した漢文体の文章は読みにくく、簡単には理解できない。本書はたいへん丁寧な作りになっていて、改題では一つ一つの論文の出典及び概説があり、解説には清沢の生涯と業績を詳しく書いている。第3部仏教の改革では、真宗大谷派の現状について、真っ向から批判するとともに、仏教界全体の衰退を論じる。2016/07/28
1.3manen
8
自力と他力の図式はわかる。タケダ製薬のようなロゴマークで、内接円と外接円の、物と心と物の関係が解明された(35頁)。「吾人は自由に就きて楽を感じ、服従に就きて苦を感ず」(88頁)。評者の自由の捉え方は、他人の自由は自分の不自由になることもあるので、他人への配慮が必要だと思うが。「吾人の行動云為は、或時は自由にして、或時は不自由なり。而して其自由と不自由との限界は時々尅々変動」(101頁)とのこと。ダイナミックな自由概念に共感した。スタティックでない。重要なところは音読してみたが、生活問題はそれなりに理解。2013/03/27
Go Extreme
1
https://claude.ai/public/artifacts/5e21e0b4-e4fc-4c76-86d7-97c446b62aee 2025/06/23
たいけい
0
ほぼ清沢満之自身が書いたであろうものを選んでコンパクトにまとめられています。100年ほど前の文章なので言葉遣いには取っつきにくいところがありますが、問題にしている事柄は現代でも問題となっているものがあります。手元に置いて、折々、読むようにしたいと思います。2013/03/26