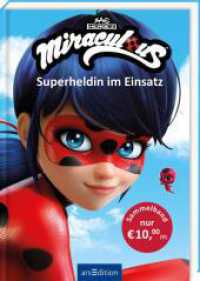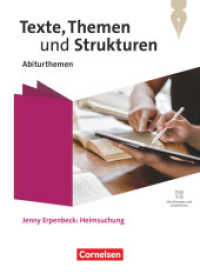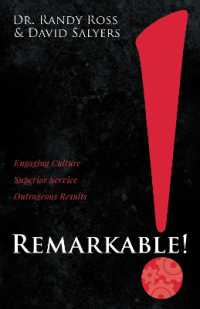出版社内容情報
砂の降りしきる町の娼館「緑の家」、密林の中の尼僧院、インディオの集落など、広大なペルー・アマゾンを舞台に、豊潤な想像力と現実描写で小説の面白さ、醍醐味を十二分に味わわせてくれる、現代ラテンアメリカ文学の傑作。
内容説明
“緑の家”を建てる盲目のハープ弾き、スラム街の不良たち、インディオを手下に従えて他部族の略奪を繰り返す日本人…。ペルー沿岸部の砂の町とアマゾン奥地の密林を舞台に、様々な人間たちの姿と現実を浮かび上がらせる、バルガス=リョサの代表作。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nobi
102
密林の逃避行と追跡、マンガチュリーア地区での抗争はこの下巻で一層濃くなって少し息苦しくなるほど。粗暴なシーンが多い中、三人の女性達ラリータ、ボニファシア、トニータの野性味の中の香気が際立つ。聖堂での結婚式などフランスの古い教会でのことのよう。それにしても最後まで「豊穣の海」のラストのように静かな無常観を呈さない。相容れない関係は収束せず時間は時に遡行する。それでも登場人物の人生が、この長編が、猛暑の夏が終わってしまうという寂しさを感じるエピローグだった。木村榮一氏の訳者解説はマルケスへの解説と同じく充実。2018/09/01
ヴェネツィア
97
これまでの物語観で読むからか、最後まで小説世界に透入することができなかった。人物群像も、その背景となる土地も混沌としたまま終りを迎える。 これはリョサの特質なのかラテンアメリカ文学の特質なのかはわからないが、とにかく物語の文法を読み解くコードを見つける必要があるのだろう。2012/01/14
榊原 香織
96
上下巻の下 話の引っ張り方がさすが。 現在と過去の会話が並列してるので日本語だとわかりにくい。スペイン語だと時制が一目瞭然で問題ないのだろうか? 40年間の物語がごちゃごちゃになって不思議な感じ。ピカソの絵みたい。濃厚な味わい。2024/06/26
NAO
74
【2021年色に繋がる本読書会】緑の家」の話になぜフシーアのくだりがいるのだろうかと最後まで首をひねっていたのだが、解説を読みフシーアの島がインディオの女たちとのハーレムだったということが分かり、なるほどこちらも「緑の家」だったわけだなと納得。なにしろ、作品の中のフシーアは、ハーレムがすっかり落ちぶれてしまったあとであり、はぶりのよさなどまったく感じられないのだから。アマゾンのインディオたちの暮らしぶり、インディオたちと共存するフシーアの生き方、アマゾン川流域に点在する小さな町、そして⇒2021/05/13
Willie the Wildcat
66
心を引き寄せる、心に残る人、物、場所・・・。”2世代”の『緑の家』が時勢を反映。共通項はアンセルモ。差別・格差への疑問が、苦闘と推察の源泉。時に他者に誤解を招く言動。但し、その死に際して垣間見る他者の愛情・愛着。ここに著者のMSGを感じる。登場するのが限定的も、神父とシスターが物語の「楔」という印象。過去と現在を行き交い、理想と現実をどこか淡々と嘆くことなく語る。よくよく考えてみれば暗い話なのだが、不思議と読後感は未来志向。蛇足だが齧歯類・・・、恥ずかしながら初めて聞いた。(汗)2016/08/06