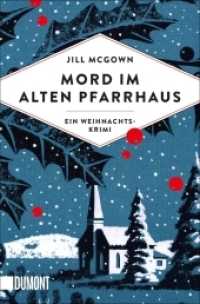内容説明
辺境の砦でいつ来襲するともわからない敵を待ちつつ、緊張と不安の中で青春を浪費する将校ジョヴァンニ・ドローゴ―。神秘的、幻想的な作風でカフカの再来と称される、現代イタリア文学の鬼才ブッツァーティ(一九〇六‐七二)の代表作。二十世紀幻想文学の古典。
1 ~ 5件/全5件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
214
青春はもうしぼみかけているのに、彼には人生は長々と続く尽きせぬ幻影のように見えた。将校に任官したジョヴァンニ・ドローゴは任地の辺境の砦に赴く。そして、いつかやって来るかも知れないタタール人の来襲を待ちながら単調な砦の生活に囚われていく。無限に続くかに見えた歳月も、ある時、後ろを振り返ると、帰り道を閉ざすように背後で格子門が閉まり、知らぬ間に全ては地平線に向かって落ちていったのを知る。自分の人生が戯れのうちに終わってしまったのだ。三十余年の歳月の流れの末、死を前にした彼に最後の安らぎが訪れる。2020/08/05
ケイ
169
砂漠は砂でなくゴツゴツとした隆起した岩。険しく厳しく、そこに居続けるには何か夢を持たねばならない。絶望的に無為な時間を何日も永遠に続けていくため、人は見えないものを見ようとする。見えないところに目を凝らし、わずかな点を凝視し、そこから想像の力を借りて何かを作り上げる。その地に無い物を求めて故郷に戻っても、やはり無い。それは何?何が足りない?何を求める?きっとそれは存在意義。自分が生きる意味。見つからない時、死だけがその代わりとなるのだろうか。残酷でいて、往々にしてそれが起こる。だから自らの足で踏み出そう。2017/08/23
sayan
154
タタール人の砂漠と称される風景描写は今夏訪れた中東地域を彷彿させる。独特な詩的な表現と淡々とした語りに普段とは異なる物語の美しい読後感に浸っていた。が、ある方の感想にハッとした。「大事なことは、これから始まる。だからずっと待っていた。ここに来たのは間違いだから、本気になれば、出て行ける。けれど少し様子を見ていた。習慣のもたらす麻痺が、責任感の強さという虚栄が、自分を飼いならし、日常に囚われ、もう離れることができない、気づいたらもう、人生の終わり」、ぞっとする感覚であり日常の自分をと急いで見直したくなった。2018/10/06
やいっち
152
何処かゴドーを待ち……を想わせる。軍人であり、戦闘状況を渇望しつつも、辺境の地でいつ来るともしれぬ敵を警戒し、同時にあまりに長い生煮え状況に、敵の姿を待望する。 ただひたすらに待ち続ける中、同僚や後輩は、出世し、あるいは町に戻っていく。気が付けば青春などどこの話というような齢になってしまっている。 切望していた(?)敵がいよいよ! が、何たる皮肉か、彼は病に倒れ、砦には邪魔な存在として、遠ざけられてしまう。 2019/01/30
buchipanda3
139
どこか幻想的な趣きを感じさせる題名。鬼才の作ということで読んでみると、思っていたよりも読み易く、さらに主人公の悩める心象を表すかのような叙情的な描写が印象深かった。若い将校のドローゴは赴任先の辺境の砦は自分の居場所ではないと思いながらも、そのまま単調な日々に身を任せてしまう。いつか特別なことが起きる、そしてまだ時間はあるのだという言い訳で。やがて年月を経て、彼が知らしめられたのは自分の思いはただの幻想に過ぎなかったということ。国も時代も不明の物語だが、まさに人生の儚げで現実的な一面が見事に描かれていた。2021/04/12
-
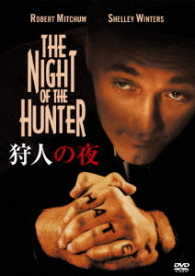
- DVD
- 狩人の夜