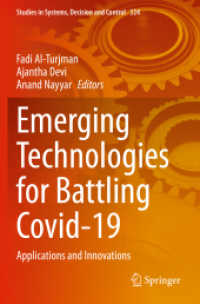出版社内容情報
興の赴くまま人間について語り続けるモンテーニュ(一五三三‐九二)の筆致には,一種いい難いあじわいがあって,われわれの心を引きつける.プルタークに傾倒し『倫理論集』を愛読した彼.自領の館に引退し,古人のひそみに倣って悠々自適の生活を送った彼.読み進むにつれて,そういう彼の人柄が読者の眼前に彷彿するにちがいない.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
NAO
52
8章「無為について」、23章「習慣について」、26章「子供の教育について」、彼の進歩的な考え方にはルネサンス期の風潮を感じるが、この時期の文筆家の中でも、モンテーニュほど公正で無欲な人はいないだろう。教育に関して今でも充分に通用する持論を持ち、終始冷静な観察眼を持ち続けたモンテーニュが、「牛のことばかり考えていたために角が生えた人がいる」という書物の記載を信じているということに大きなギャップを感じ、彼が生きていた16世紀という時代を感じるが、だからといって、もちろん、彼への敬愛が薄れるわけではない。2016/03/03
tonpie
39
寝る前に読むと眠くなる古典の筆頭。最初の方は貴族や将軍が、どうやって戦争で生き延びられたか、恥をかかずに済んだか、という話題が多い。セネカやギリシャ哲学の引用が多く、作者が純粋に「真実」を求めていることは確か。16世紀後半、フランスの貴族が自分の認識のためだけに大真面目で書いた素人談義だ。宮廷勤めとボルドーの判事を引退して暇な荘園領主さまなので、気になる問題にこだわると、とことんしつこい。読者のウケなど、全く意識していない。2023/12/30
Y2K☮
37
エセー。現代人がイメージする随筆のレベルに非ず。悟りと戒めの書だ。哲学とは歴史とは勉強とは教育とは、そして言葉とは読書とは。現実的な面しか見ないと人は目先の欲に溺れて卑しくなる。逆に崇高な理想ばかりを追っていると身近な日常の尊さを見下す。群れて馴れ合うばかりでは堕落するが殻の内に閉じこもるのも独善的な思い上がりを育む。井上達夫の云っていた正義の背中が少し視えた。思い描く己の正しき姿。そこに近づくための正しい努力が楽しくないわけない。肝はバランス感覚。そして知識ではなく判断力。全六巻。少しずつ読んでいこう。2019/05/14
踊る猫
36
古い表現になるが、「懐の深さは曙並み」((c)スチャダラパー)という言葉が思い浮かぶ。読んでいてこちらの違和感や怒りや不安を穏やかに溶かす、円やかな話題の広がりと筆致がクセになるのだった。書かれている結論はそれだけを取り出せば意外と今の目からすると凡庸なものに映るが、しかし今に至るも読むに耐え得る強度を備えている。それはむしろこの本が未だにパクられるネタ元として君臨している、その風格にもよるのではないか。曙の名を出してしまったが、これが横綱相撲というやつか。珍奇で過激な文章を書くだけが「エッセイ」ではない2020/01/07
風に吹かれて
18
堀田善衛『ミシェル城館の人』でモンテーニュとその時代のことを知って読む『エセ―』は興味深い。膨大な哲学や歴史書などからの引用で各々のテーマに関わるモンテーニュの考えを包み込みつつ、当時の世相や考え方を批判的に、ときに擁護的に記す。時代が中世ゆえ、現在から見ると差別的と思えるところもないわけではないが、考えるために知る、知識は量ではなく質としながら「自然が示してくれた坦々たる大道」(p384)に向けた思索が展開される。読んでいると、モンテーニュから思索に誘われているように感じさせられる。2019/03/04