内容説明
「はやり唄」は、明治・大正期の民衆の喜び、哀しみ、怒りの思いを表現して広く愛唱された。街角の唄、寄席の唄、座敷の唄、壮士の唄、書生の唄、ヴァイオリン演歌、劇場の唄、映画の唄の8テーマに分類、127曲を精選して、注解を付した。「カチューシャ」「金色夜叉」「篭の鳥」などの唄は、時代を超えて今なお日本人を魅了してやまない。
目次
街角の唄
寄席の唄
座敷の唄
壮士の唄
書生の唄
ヴァイオリン演歌
劇場の唄
映画の唄
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
56
明治、大正のはやり唄をまとめた一冊。「歌は世につれ世は歌につれ」という言葉があるが、本書を読むと歌が世相と不可分の関係にあるのがわかる。有名な「宮さん宮さん」から始まり、明治だと「西郷隆盛の唄」とか川上音二郎、大正だと『金色夜叉』や藤村操。歌詞を見ていると何故か聞いた事はないけれども、そこはかと懐かしい感じがする。あと乱歩の「白昼夢」中に歌われている歌が「チリツプ節」である事とか、『ドグラ・マグラ』中にあるのが「カチーシャの唄」だとか、宮沢賢治の詩に引用されてたりとか、文学方面から見てもこの本面白いなあ。2017/05/22
スローリーダー
6
明治·大正期に流行った唄を纏めた労作。お上からは愚劣で下等と蔑まれ、取締の標的にされた唄もあった。演説調やがなる節もあり、唄のバリエーションは多彩だ。和と洋が折衷し、時代と共に西洋化が進んだ。所収127曲の内28曲を聴くことが出来た(歌詞は本と大分違う)。残りは字面を辿るばかりだった。日本でレコードが吹き込まれる大正以前の曲(特に壮士の唄、書生の唄)は聴くことが困難だった。映画の唄には今でも馴染みのあるものがある。『江戸端唄集』と併せて日本の庶民の音楽の歴史が偲ばれる。2023/03/05
天婦羅★三杯酢
3
神保町はやはり魔都である。本当は別の本の続編を買おうと思って入っただけなのに、いつのまにやらあれこれと買ってしまう。明治大正の、壮士や書生が歌った歌、座敷や寄席、劇場で歌われた歌。それはある種正史からは忘れられた物となっているけど、やはり日本の近代を語るときに欠かせない資料ではあるだろう。わたし的には、たとえば「はいからさんが通る」や「パタリロ!」などに断片的に引用されていた唄をいくつも発見し、それらが決め手となって購入を決めたのである。2016/09/30
大臣ぐサン
2
明治・大正期の流行歌を収録。街角の唄、寄席の唄、座敷の唄、壮士の唄、書生の唄、ヴァイオリン演歌、劇場の唄、映画の唄、の8ジャンルに分かれているが、あくまで便宜上の区分だ。ジャンル区分を見るだけで、時代がプンプン香ってくる。解説から当時のはやり唄が俗悪なものとされ、忌み嫌われていた事情が分かる。また、松井須磨子のエピソードから、演劇とレコードという新しいジャンルが流行歌を広めることとなった背景も興味深い。同時にしばしば官憲から流行歌が禁止されたという事情もまた興味が尽きない。楽譜がついていないのが残念だ。2021/11/03
めっちー
2
明治・大正の流行り歌を寄席、座敷、映画、劇場、壮士、バイオリン、書生、街角とジャンル分けして掲載した本。明治初期のは戦の臭いがしたり、日清戦争後は硬派路線が薄くなる等当時の社会情勢を反映している。「カチューシャの唄」や「オッペケペーぶし」等有名な唄もあるが、長閑な唄や風刺の唄、西郷隆盛の唄もある。ヴァイオリン、劇場、映画は女性の悲哀の唄が多く、貧しさ、悲恋、芸者の恋等全体的に生きる事の辛さが漂う。明治時代は音楽や音楽家の地位が低かったが、西洋もベートーヴェン辺りまでは低かったので、特別おかしな事ではない。2021/07/05
-

- 電子書籍
- クラス最安値で売られた俺は、実は最強パ…
-

- 電子書籍
- ダークサモナーとデキている【分冊版】 …
-

- 電子書籍
- 転生したら没落貴族だったので、【呪言】…
-

- 電子書籍
- 毒りんごcomic 69 アクションコ…
-
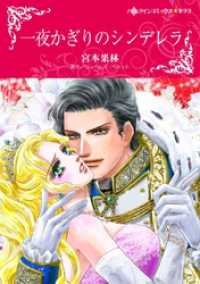
- 電子書籍
- 一夜かぎりのシンデレラ【分冊】 11巻…




