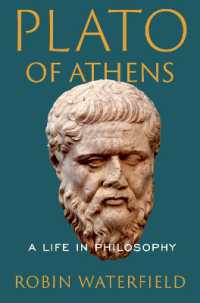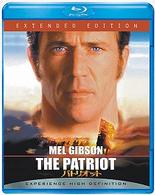出版社内容情報
井上井月(1822―1887)は,天保期から明治初期にかけて信州伊那谷を漂泊,一所不住の数奇な生涯を終えた俳諧師である.所謂「月並俳句」の時代とされる近世俳諧の沈滞期にあって,ひとり芭蕉の道を歩いた越格孤高の俳人である.井月の発句,俳論を精選して,初めて詳細な注
内容説明
井月は、明治期、信州伊那谷に滞留しつつ漂泊、数奇な生涯を終えた行脚俳人(1822‐1887)。所謂「月並俳句」の時代とされる俳諧の沈滞期にあって、ひとり芭蕉の道を歩いた越格孤高の俳人である。井月の発句、俳論を精選して、初めて詳細な注解を付す。また、井月の文業を、最初に世に紹介した下島勲、高津才次郎の井月論をも併せて収録し、近世俳人最後の高峰の全貌を伝える。
目次
発句篇(春の部;夏の部;秋の部;冬の部;新年の部)
俳論篇(俳諧雅俗伝;用文章前文)
参考篇(略伝;奇行逸話;俳人井月;井月の追憶と春の句;乞食井月と夏)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
32
「このせち辛い近世にも、かう云ふ人物があつたと云ふ事は、我々下根の凡夫の心を勇猛ならしむる力がある」(芥川龍之介)春夏秋冬毎にまとめられた俳句、読んでいると何やらほっとするようなものを感じる。妙に素直で心の中にすとんと落ちるような句が多いように感じられた。作中の「俳諧雅俗伝」の通り。この人といい山頭火といい、放下というか無一物の境地に至った人は、心の持ちようが我々とは変わってくるのかなあ。俳句以外に年表や逸話も収録されており、人となりもよくわかるようになっている。彼が世に知られるまでをまとめた解説も必見。2013/04/30
1.3manen
7
自己韜晦(323頁)。表に出ない。一市民として詠む。鶯が出てくるが(33頁~)、今年は鳴き声を聴かない。先週金曜日はトンボを見た。季節感を喪失した今だからこそ、本書の放つ価値は大きい。286「頂を花とながめて富士の山」(61頁)。世界遺産の価値を汚さぬよう。430「白雨(ゆふだち)の限(かぎり)や虹の美しき」(87頁)。限=終り。虹が終わりの象徴と見るのは凄い。評者は平和を見るが。838「新蕎麦に味噌も大根(だいこ)も褒められし」(157頁)。からみ大根のつけ汁だ高遠は。明治生れの故祖母もだいこ と発音。2013/05/14
シンドバッド
6
解説に、ボリュームを、割くのであれば、発句をもっと増やして欲しかった。文庫は、研究者の為のものではないことを、岩波茂雄も、表明しているのに残念。井月を、発句を通して、もっと自分なりに、知りたかった。2014/04/23
Asakura Arata
4
下島勲、高津才次郎の文が、井月の人となりを想像させて興味深い。高遠あたりに彼の句碑がたくさんあるので、巡ってみたい。意図的に詠むところが全くなく自然そのものの句がとてもしっくりくるし、自分の臨床態度と共通するところがあり、見習っていきたい。2023/08/21
あや
4
B型なので基本的に自由が好きで漂泊する詩人に憧れる。芭蕉もそう。江戸末期にこんな詩歌を熱愛する俳人がいたことを岩波書店のツイッターのツイートで知り早速注文したことが手に取ったきっかけでした。行き倒れてまでも詩歌を愛する心。詠んだ句も春には春の句が沁み冬には冬の句が沁みるようなその季節ごとに手に取りたくなるような愛読書です。2020/03/14