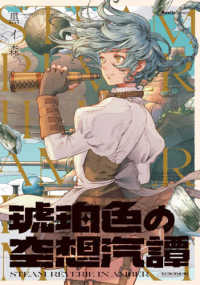出版社内容情報
主人公源氏の胸中に深く刻まれた継母藤壺への思慕を出発点として,栄光と寂寞の生涯を辿った四四帖.そして息子薫の世界を描く宇治十帖.始発から終末まで七十年余の時代を追うこの物語には王朝文化の粋が結集され,後世に絶大な影響を与えた.三条西実隆筆青表紙証本を底本とし,複雑な文脈を解きほぐす注を施す.
内容説明
華やかな宮廷生活の表裏を、これほど鮮やかに美しく描き上げたロマンは他に類をみない。本書は源氏研究に一期を画した硯学の校訂になる。殊に、複雑な文脈を系統づける傍注は大きな特色といえよう。本巻には「桐壼」から「花散里」にいたる11篇を収録。
目次
桐壼
帚木
空蝉
夕顔
若紫
末摘花
紅葉賀
花宴
葵
賢木
花散里
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
i-miya
47
2013.04.09(つづき)山岸徳平校注。 2013.04.09 左馬頭「なりのぼれども(出世していっても)、もとより、さるべき筋ならには(血筋がよくないものは)世の人の思えることも、さはいえども、なお異なり。 また、もとは、やんごとなき筋なれど、世に経るたづき少なく、時、うつろいて、おぼえおとろえぬれば、心は心として、ことたらず、わろびたることども、出でくるわざなめれば、とりどりにことわりて、中の品にぞ、おくべき。 受領といって、人の国のことにかかずらい、2013/04/09
i-miya
38
2013.02.18(つづき)山岸徳平校注。 2013.02.18 左馬頭、大方の世(男女の仲)につけて見るには、咎(とが)なきも、「わが物」と、男(おのこ)がうち頼むべきを選ばむに、女が多かる中にも、男には、えなん思い定むまじかりける。 男の朝廷(おおやけ)に、仕うまつり、はかばかしき世のかためとなるべきを、取り出さんには、難(かた)なるべしかし。 2013/02/18
i-miya
35
2013.01.24(つづき)山岸徳平校注。 2013.01.23 光源氏「その品々や、いかに。いづれを三つの品に置いてか、分くべき。もとの品、高く生まれながら、身は沈み、位、短くて、人なげき者と、又、直人の上達部などまで、なり昇りたる。我は顔にて、家のうちをかざり、「人に劣るものではない」と思われる。そのけじめをば、いかに分けるべきか」 ※直人=五位以下の人。地下人を指していう。 2013/01/24
i-miya
33
2012.10.30(つづき)山岸徳平校注。 2012.10.30 右大臣は、かしづき給う四の君に、婚(あわ)せ給えり。 源氏におとらず、右大臣が少将をもてかしづきたるは、両家ともにあらまほしき御あはひどもになん。 源氏の君は、帝の常に召しまつはせば、心安く里住まいもえし給わず。 心の中(うち)には、tだ藤壺のありさまを「類なし」と思い聞こえて「さようならむ女の人をこそみめ。藤壺は似る人もなくおはしけるかな」 2012/10/30
i-miya
32
2013.07.11(つづき)山岸徳平校注。 「さる女が、宮仕えに出で立ちて、思いがけない幸い多い」などというと、源氏、「すべて女は、賑わしきによるべきなんなり」と笑うのを、中将、「他人の云うように心得ずおっしゃる」といって、源氏を憎む。 馬頭「もとの品、時世の思(おぼ)え、うちあい、やんごとなきあたりのうちうちのもてなし、気配、おくれたらんは、更にもいわず」、「なにをして、女が、かく生(お)い出けん」と人にいうかいなく思える。 2013/07/11