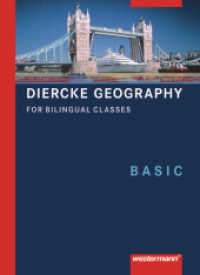出版社内容情報
坂上 香[サカガミ カオリ]
著・文・その他
内容説明
人は、ひとりでは罪と向き合えない。日本初となる刑務所内での長期撮影、10年超の取材がここに結実。
目次
プロローグ「新しい刑務所」
ある傍観者の物語
感情を見つめる―四人の物語
隠さずに生きたい
暴力を学び落とす
聴かれる体験と証人―サンクチュアリをつくる
いじめという囚われ
性暴力 光のまだ当たらない場所
排除よりも包摂
助けを諦めさせる社会
二つの椅子から見えたもの
被害者と加害者のあいだ
サンクチュアリを手わたす
罰の文化を再考する
エピローグ「嘘つきの少年」のその後
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
がらくたどん
79
平成19年・20年に日本で4か所の官民混合運営型刑務所が運営開始した。その中の犯罪傾向が進んでいない男子受刑者対象の「島根あさひ社会復帰促進センター」での「回復共同体(TC)」プログラムを映像化した際の取材をまとめたルポ。「問題には皆で対処し、失敗しても解決に向けて努力すれば許され、傷ついたと言う権利が認められ、それを語れば耳を傾けてもらえ」る地縁血縁によらない共同体の力を使って「感情の筋肉を鍛え」問題からの回復を目指す手法は一部海外ではすでに犯罪者の矯正から広く一般的な教育プログラムへと展開している→2023/09/13
おたま
69
ドキュメンタリー映画監督・坂上香が、「島根あさひ社会復帰促進センター」(略称「島根あさひ」)という官民合同の刑務所で撮影した映画『プリズン・サークル』の内容と、そこで削除された部分も増補して書かれた。特に島根あさひで行われているTC(Therapeutic Community=回復共同体)という取り組みに焦点を当てている。普通の刑務所で行われている、罰としての訓練や拘禁とはまったく異なる。確立されたプログラムに沿いながら、受刑者自らが共に対話を繰り返して「回復」していくことを求める。2023/02/09
ネギっ子gen
65
【人は、ひとりでは罪と向き合えない】 日本初となる刑務所内での長期撮影の結果が、本書と映画という形で結実。その著作版。受刑者が互いの体験に耳を傾け、本音で語り合う。そんな更生プログラムをもつ男子刑務所が、島根県浜田町旭町にある。受刑者同士の対話をベースに犯罪の原因を探り、更生を促す「TC(Therapeutic Community=回復共同体)」というプログラムを導入している、日本で唯一の刑務所でもある「島根あさひ社会復帰促進センター」。以下は、いつもの。⇒ https://note.com/genok/2022/05/08
たま
64
以前に読メで感想を見かけ、気になっていた本。重い内容で考えさせられた。著者の坂上香さんは島根あさひPFI刑務所でTC(回復共同体)と呼ばれる更生プログラムの模様を映画に撮影。この本はその記録でもある。育児放棄、DV、いじめ等を経験し抑圧してきた受刑者が過去と向き合い自己の犯罪、被害者との関係を捉え直す。形式的な反省文を書くのではなく、少人数のグループで話し・聞きあい、ロールプレイで再体験するのである。僅か40人(全受刑者数は4万人)が参加するプログラムだが、再犯率が低いなど実効性があるようだ。→ 2024/02/18
夜長月🌙新潮部
62
犯罪者の更生について考えさせられました。罰として刑務所に入れるだけで人が生まれ変わる訳がありません。「島根あさひ」という更生プログラムを持つ刑務所があります。ここでは、人の再生のためにディスカッションや討論が行われます。罪が生まれた背景に何があるでしょう。親からの暴力やネグレクト、性被害などが語られて心理的に解決されることがないと反省などは生まれません。負の連鎖を断ち切るにはこの社会に一人でも理解者を増やすことが大切です。2024/06/12
-

- 電子書籍
- アプリコットファズ【分冊版】 13 電…
-

- 電子書籍
- 【フルカラー】ツキマトイ。~鳴り止まな…