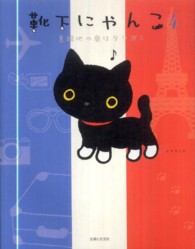出版社内容情報
人間本性に関わる根源的な問いに取り組むチョムスキーの思索を、旧知の哲学者が聞き手となって掘り下げる。
内容説明
なぜ我々人間はことばを持つのか。我々はことばで何を問い、何を語るのか。我々は自ら発した問いにどこまで答えることができるのか。―人間の認識の限界に挑み続けてきた言語科学者チョムスキーが今、旧友の哲学者を前に、あくなき問いを語り始める。言語、科学、心、道徳、人間本性をめぐるロング・インタビュー。
目次
第1部 言語と心の科学について(言語・機能・コミュニケーション―言語と言語使用について;形式的言語理論を生物学に組み込むことと、人間の概念に特有の性質について;表示と計算;人間の概念についてのさらなる考察;言語研究に関する省察 ほか)
第2部 人間本性とその研究(人間本性と人間の理解について;人間本性と進化―社会生物学および進化心理学についての考察;人間本性、再び;道徳性と普遍化;楽観的展望とその背景 ほか)
著者等紹介
チョムスキー,ノーム[チョムスキー,ノーム] [Chomsky,Noam]
1928年、アメリカ合衆国ペンシルヴェニア州フィラデルフィア生まれ。学部生時代をペンシルヴェニア大学で送り、1951‐55年は同大学大学院に籍を置きつつ、ハーバード大学のジュニアフェローを務める。1955年、ペンシルヴェニア大学より言語学の博士号(Ph.D.)を受ける。1955年よりマサチューセッツ工科大学(MIT)に勤務し、現在は同大学のインスティテュート・プロフェッサー、名誉教授
マッギルヴレイ,ジェームズ[マッギルヴレイ,ジェームズ] [McGilvray,James]
1968年、イェール大学にてPh.D.(哲学)を取得。現在はカナダ・マッギル大学名誉教授。専門は心の哲学・言語哲学・形而上学
成田広樹[ナリタヒロキ]
2011年、ハーバード大学にてPh.D.(言語学)を取得。早稲田大学高等研究所、日本大学生産工学部勤務を経て、現在は東海大学文学部英語文化コミュニケーション学科特任講師。専門は理論言語学・認知科学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
loanmeadime
くにお
しのジャッキー
御光堂
-

- DVD
- 裁判長!トイレ行ってきていいすか
-

- DVD
- 君はまだ、無名だった。