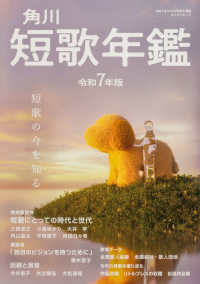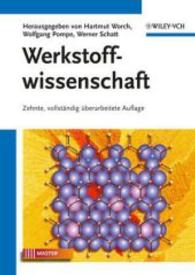出版社内容情報
実はカタツムリは、進化研究の華だった。行きつ戻りつしながらも前進していく研究の営みと、カタツムリの進化を重ねた壮大な歴史絵巻。
内容説明
なんだか地味でパッとしないカタツムリ。しかし、生物進化の研究においては欠くべからざる華だった。偶然と必然、連続と不連続…。木村資生やグールドらによる論争の歴史をたどりつつ、行きつ戻りつしながらもじりじりと前進していく研究の営みと、カタツムリの進化を重ねて描き、らせん状の壮大な歴史絵巻を織り上げる。
目次
1 歌うカタツムリ
2 選択と偶然
3 大蝸牛論争
4 日暮れて道遠し
5 自然はしばしば複雑である
6 進化の小宇宙
7 具と麻雀
8 東洋のガラパゴス
9 一枚のコイン
著者等紹介
千葉聡[チバサトシ]
東北大学東北アジア研究センター教授、東北大学大学院生命科学研究科教授(兼任)。1960年生まれ。東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。静岡大学助手、東北大学准教授などを経て現職。専門は進化生物学と生態学。大学院修士課程でカタマイマイに出会い、小笠原諸島を出発点に、北はシベリア、南はニュージーランドまで、世界中のカタツムリを相手に研究を進める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たま
64
吉川浩満さんの『理不尽な進化』に挫折し(良い本ですが引っ張り回される感が辛い)、この本へ。カタツムリ研究を通じて進化生物学がいかに発展してきたかを、19世紀後半から現代まで実際の研究と学説に即して概観する。複雑な内容が見事にまとめられ、進化生物学の適応説一辺倒ではない螺旋状の展開、分子生物学や古生物学の参画、日本での研究の重要性など、高校理科どまりの私にもぐいぐい読ませる著者の筆力に驚嘆しながら読んだ。2017年毎日出版文化賞。私が読んだのは岩波科学ライブラリー版だが、先日岩波現代文庫に入ったようだ。2023/07/21
チャーリブ
48
傑作というものは最初の数行を読んだだけで分かるものです(逆も真ですが)。本書はそんな1冊。題名は、かつてハワイの人たちがカタツムリが歌うと信じていたことから来ています。ハワイに育った少年ギュリックはハワイのカタツムリ、ハワイマイマイに魅せられてその採集に明け暮れていました。やがて宣教師となった彼は、ダーウィンの進化論を知り、ハワイマイマイのコレクションを携えてダーウィンを訪ねていきます。そこから進化とカタツムリを巡る「らせんの物語」が始まります。読後は世界を見る目が変わります。◎ 2022/09/13
やいっち
34
童謡『かたつむり』「でんでんむしむし かたつむり おまえのせなかは どこにある やりだせ つのだせ あたまだせ~♪」を子供の頃、折々歌った記憶がある。今も歌われているのだろうか。というか、昔は家の近隣でも梅雨の季節などよく目にしたものだった(カタツムリと「でんでんむし」は同じ)。といいつつ、本書はそんな童謡を扱った本ではない。また、カタツムリがホントに『カタツムリ』を歌うわけじゃない。だが、「歌うカタツムリ」という本書の題名は伊達につけられているわけではない。2017/10/10
かもすぱ
24
ダーウィンから始まる進化論史をドラマチックに綴った本。進化論において自然選択(自然による種の淘汰)が重要なのか、それとも遺伝的浮動(偶然得られた形質が偶然生き残ること)が重要なのか、カタツムリに魅了された生物学者がカタツムリでマジ論戦を繰り広げる。あいつが伏線だったのか!いう展開が何度も繰り返されるどんでん返しと過去の理論の亡霊の熱い展開。それでも着実に前進する全体としての進化論。まさに進化と螺旋の物語、サブタイトルが熱い。面白かった。2020/03/31
tom
22
面白い。研究者の進化研究のバトルの歴史。あれやこれやと部分的に知っていることはあるものの、通史として読めたのがありがたい。その歴史と変遷と、著者が考える落ち着きどころ、これを丁寧かつシンプルに書いてくれていて、ああ、そうだったのですかと思いながら読了。もっとも、頭に入ったのは20%くらいか、もう一度読み直したら50%くらいになるかもしれない。再読しようと思う本。2023/08/11
-
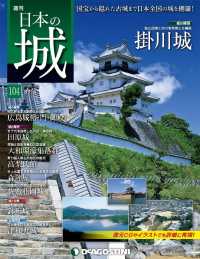
- 電子書籍
- 日本の城 改訂版 - 第104号
-
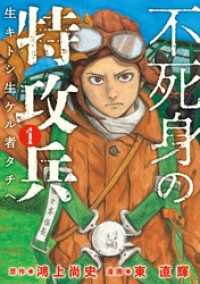
- 電子書籍
- 不死身の特攻兵(1)