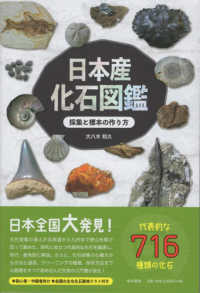内容説明
原発事故後、行政や研究機関からデータそのものは発表されても、その解釈が被害を過小にみせる方向にゆがんでいる例が多数ある。公式発表はどのようにゆがんでいるのか、そして、データはどのように読み解くべきなのか。発表や報道を鵜呑みにするのではなく、不十分なデータからでも科学的にいえることを導き出すために、自ら計算し確認する方法を読者に示す。好評を得た『原発事故と科学的方法』の著者による第2弾。
目次
第1章 過小評価の論理―鼻の被曝について
第2章 チェルノブイリでの甲状腺がん―公式発表の前提と私たちに必要な情報とのちがい
第3章 チェルノブイリでの甲状腺がん以外の健康被害―既存のリスク係数よりも大きすぎるからありえない?
第4章 甲状腺がん発生に「地域差はない」のか?―県民健康調査からみえること1
第5章 被曝量推定は信頼できるのか?―県民健康調査からみえること2
第6章 これからどうなるかを考える
第7章 まとめ
著者等紹介
牧野淳一郎[マキノジュンイチロウ]
1963年生まれ。1990年東京大学大学院総合文化研究科(広域科学専攻)博士課程修了。東京大学助手、助教授、国立天文台教授、東京工業大学教授を経て、理化学研究所計算科学研究機構に勤務。Gordon Bell賞(1995年から7回受賞)、日本天文学会林忠四郎賞(1998年)受賞。主な研究分野は理論天文学、恒星系力学、並列計算機アーキテクチャ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
那由田 忠
7
感想が「専門」バカの人は困る。専門が天文で統計が詳しいが、放射線ではない。鼻血が出る可能性を検討しありえると言う。ICRPのデータを使って、鼻の中で放射性粒子がつかまると、鼻腔の被曝線量の計算から、身体全体としてはわずかな線量でも鼻の粘膜には大きな影響が出ると。しかし、身体への影響は実効線量で見るが、その計算を示さない、2桁低いのに。さらにこの線量はピーク時に可能な値だ。問題となったのは原発見学者の鼻血で、柏市での鼻血の話さえ聞いた。「専門家」が別分野で非難する無理がある。岩波も出版の責任を負うべきだ。2015/06/18
calaf
4
科学的な方法では、分からないというのが結論という事。つまり、分からないだけであって、影響があるともないとも言えないという事。これをないと言い切ろうとしている発表に関して文句を言うのはその通りだとはおもうのだけど、現実問題としてはどちらかに白黒つけないと何も進まないのも確か。そしてその結論を出そうと努力していないというのも現実でしょう。そういう現実下で個人的にはどうすればいいのか...結局分からない...2015/05/09