出版社内容情報
天球のふしぎな運行から天変地異や運命を予測する占星術はいかにして天文学という科学となったか。その背景には、バビロニアや古代ギリシアの成果をどん欲に取り入れた中世イスラーム文化の強い影響がある。残された文献から知られざる真実を追う。
内容説明
古代より、天体のふしぎな運行を予測し、天変地異の前触れを読みとることは、国の政治を司ることにも等しかった。しかし、そうした占星術に端を発する天文学が科学として成立するには、バビロニアや古代ギリシャの成果をどん欲に取り入れようとした中世イスラームの存在が不可欠だったのである。なぜか。その謎を追って知られざる事実を明らかにする。
目次
1 近代科学の起源としての天文学
2 ペルシャ人国家アッバース朝の成立
3 アッバース朝と占星術
4 最先端の天文学としてのインド天文学
5 アッバース朝宮廷と論証
6 アッバース朝宮廷の学者たち―宮廷の助言者として
7 プトレマイオス天文学の再発見
8 プトレマイオス批判からコペルニクスへ
著者等紹介
三村太郎[ミムラタロウ]
1976年生まれ。2008年東京大学大学院総合文化研究科(広域科学専攻相関基礎科学系)博士課程修了(学位(学術))。現在、カナダMcGill大学イスラーム学研究所助手(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
calaf
5
プトレマイオスの『ハルマゲドン』(天動説)と、コペルニクスの『天球回転論』(地動説)とを繋ぐ間には、イスラム世界が大きな役割を果たしていた...という話。ほとんど知らなかった/習ったけど忘れていた事ばかりでした。という事で、私的にはインパクト大な本でした。2012/01/27
takao
3
ふむ2022/08/20
Sakurai Daisuke
1
天文学が占星術の影響を受け学問として進化したことはなんとなくは知っていたが、ここまで宗教と深く関わっていなかったことは知らなかった。2020/08/22
はーと
1
再読。イスラーム世界でも、問題解決型の学問から論証重視に50年間ほどで進展した。という下りなど興味深い。2016/01/03
あずみな
0
プトレマイオスの天動説からコペルニクスの地動説に至るまでの流れを著した本。この2説がどのように生まれたかはある程度の人が知っているだろうが、その2説の「間」はあまり知られていないだろう。この本ではその「間」をイスラーム世界に注目しながら説明しており、とても興味深い内容だった。2024/01/26
-

- 電子書籍
- 可愛すぎる幼馴染のための成り上がり戦記…
-

- 電子書籍
- ひげを剃る。そして女子高生を拾う。【分…
-

- 電子書籍
- ご飯つくりすぎ子と完食系男子 【分冊版…
-
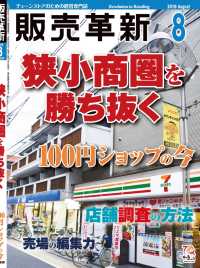
- 電子書籍
- 販売革新2018年8月号 - チェーン…





