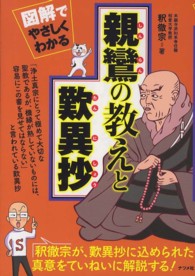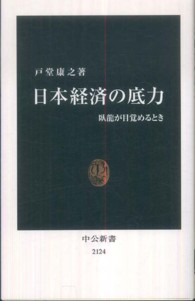出版社内容情報
子どもや若者が生活時間の多くを過ごす学校。授業や課外活動での濃密な人間関係を通して,かれらが日々呼吸している「空気」とはどのようなものか。それは,子どもや若者にどんな作用を及ぼしているのか。勉強(学力)/友だちとの関係/先生との関係/進路(将来)の4つの扉から,学校に立ちこめる「空気」をすくい取る。
内容説明
「学力」と「生きる力」の間には何があるのか?自分をウチと呼ぶのは「普通」であることの表現?友だち関係、先生との関係のリアルとは?「学力」/友だち/教師/将来という4つの扉からせまる、学校の「空気」。
目次
1 「学力」―差異の刻印(「学力」をどう考えるか;2つの「学力」の分布と相互関係 ほか)
2 友だち―教室という劇場/戦場(教室の中の島宇宙;クラス内での「地位」 ほか)
3 教師―親密性の濃淡(やさしくなった教師;親密さの濃淡を左右するもの ほか)
4 将来―野心の偏在、又の強迫(それぞれの将来像;友だち関係が将来に落とす影 ほか)
著者等紹介
本田由紀[ホンダユキ]
1964年生まれ。東京大学大学院教授。教育社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
katoyann
19
2011年刊。東京大学教育学部の教育社会学調査実習というゼミで実施した神奈川県の公立中学校に通う生徒へのアンケート調査を基に「共同性」を重視する生徒のコミュニケーションの志向性について分析している。生徒の価値観は学力高位層と低位層で分かれるわけだが、コンサマトリー化といって学校生活そのものを親密な人間形成の場として捉える意識が高まり、かつ「キャラ」を演じることによってクラスの雰囲気を良くしようとするコミュニケーションの圧力が高くなっていると指摘している。若者文化のノリを理解するのに役に立つ本だろう。2024/09/17
みのゆかパパ@ぼちぼち読んでます
10
中学2年生を対象にしたアンケートの結果から、彼らが多くの時間を過ごす学校の「空気」に迫り、それがどんな影響を与えているかを探った本。中2の娘がいるので興味深く読み、なるほどと思う分析もあったが、なんといっても1回きりの調査の分析なので、いまの特徴が浮かび上がらないのが痛い。携帯やネットの発展などといった社会の変化が学校の「空気」に及ぼす影響にふれず、子どもたちの生の声をあまり取り上げなかったのも物足りない。この問題に向き合う著者の研究姿勢に共感するだけに、時代の変化のなかでいまを読み解く書を期待したい。2011/07/08
ケン五
10
学校の空気を、雰囲気や事例から考察したのではなく、中学生から取ったデータから分析している本。どちらかというと、研究書を一般向けに分かりやすく噛み砕いた感じで、普段なんとなく、そうなんじゃないかなーと思っていたことが、数値で明らかになって、なるほどと思った。この本は、あくまでも学校がどんな空気なのかを明らかにするだけで、だからどうすべきと提案していないところも面白い。2011/03/24
てん
8
中学校でクラス内の「地位」が(低位・いじられ)に属する人ほど自分の気持ちと違っていても、人が求めるキャラを演じてしまう。また仲の良い友達でも自分のことをわかっていないと感じている。高校生になったら今と違うキャラになりたい、と答える人も多いけど、(女子・いじられ)に関してはその割合が高くはなくて、きっと諦めとか変化に対する恐怖があるのかもしれないと思った。2022/12/01
shouyi.
5
本書は、学校の「空気」を「学力」、友だち、教師、将来という切り口で捉えた本である。このうち「学力」と将来は「目的性」、友だちと教師は「共同性」を意味する。共同性の獲得が目的性を希薄する事があるという指摘もあり、学校での若者の生きづらさを表しているのかもしれない。2022/03/27