内容説明
西洋近代との出会いの中で急速に制度化された「日本美術」。その過程で一度は見失われかけた手仕事の魅力と価値が、若き美術家たちによって再発見された。日清・日露戦争、さらに第一次世界大戦を経て大きく変容する帝国日本の社会の中で、女性や農民、名もない職人たちとの協働を通じて新しい「美」の創造をめざした、富本憲吉、藤井達吉、山本鼎らの実践と葛藤をみつめ、その歴史的意義を問い直す。
目次
プロローグ―手仕事の居場所
第1章 「日本美術」の生成―美術政策と西洋近代(「日本美術」揺籃の場としての博覧会―ウィーン万国博覧会を起点として;産業と「美術」―「美術」の制度化(1)
ジャンルのヒエラルキーと教育制度―「美術」の制度化(2)
「手芸」と女性の国民化―もう一つの国家プロジェクト)
第2章 帝国の工芸と「他者」―富本憲吉の視線の先に(日露戦争後の美術界;消費社会の美術工芸;女性、野蛮、農民の手仕事―「他者」との遭遇)
第3章 大正期美術運動の展開―手芸、農民美術、民芸(社会問題としての美術工芸;工芸、手芸とアマチュアリズム―藤井達吉と姉妹たち;農民美術運動と農村政策の時代―山本鼎の実践と蹉跌;「個」と協働―富本憲吉と民芸運動)
エピローグ―「手仕事の国」日本はどこから来たのか、そしてどこへ行くのか
著者等紹介
池田忍[イケダシノブ]
1958年生。東京女子大学文理学部史学科卒業。学習院大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。現在、千葉大学文学部教授。日本美術史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
takao
masoho
-

- 電子書籍
- ループ10回目の王女様【タテヨミ】第7…
-
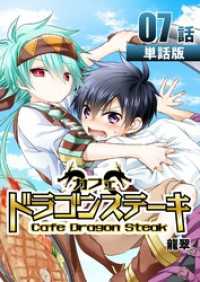
- 電子書籍
- カフェ ドラゴンステーキ 第7話【単話…






