出版社内容情報
関東大震災以降、音響テクノロジーの進化と複製技術の発展によって、大きな転換期を迎えた音楽産業の様相を叙述する。レコード会社は、作詞・作曲・演奏・歌唱を統括して、流行歌謡の大ヒットと大量消費を巧みに主導していった。併せて、ラジオやトーキーをはじめ同時代におけるメディアの強化と人びとの知覚の変容を描く。
内容説明
復興期におけるテクノロジーとメディアの刷新は、知覚の変容と共に大量消費時代の音楽を誕生させた。第三巻では、ラジオやトーキーの出現、レコード会社主導による流行歌謡の大ヒットなど、音楽が大量に消費される時代の様相が叙述される。
目次
歌工場の始動
第1部 モダン相の歌(行進曲歌謡;「君恋し」;「東京行進曲」)
第2部 古賀政男の二つの顔(「酒は涙か溜息か」;明朗歌謡)
第3部 モダン相のB面(新民謡;股旅小唄)
第4部 勝太郎に聴く近代音曲(「島の娘」;「東京音頭」;「さくら音頭」)
第5部 モダン女子を歌う(小市民歌謡;モガ歌謡;ネエ小唄)
著者等紹介
細川周平[ホソカワシュウヘイ]
1955年生まれ。東京芸術大学大学院音楽研究科博士課程修了。現在、国際日本文化研究センター名誉教授。専門分野は近代日本音楽史、日系ブラジル文化史。著書に、『遠きにありてつくるもの―日系ブラジル人の思い・ことば・芸能』(みすず書房、2008年、読売文学賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takao
1
ふむ2024/10/20
水紗枝荒葉
1
シリーズ第三弾。本巻では「歌は世にもつれ世は歌にもつれ」を標語に、レコード産業が急速に拡大した1928-38年頃の歌謡曲を扱う。この年代を扱う類書は多いし、本巻も「君恋し」「東京行進曲」「東京音頭」といったキーソング、古賀政男・小唄勝太郎といったキーパーソンは外さない。それでも作品・人・社会のそれぞれに多角的な分析を加えながら研究者らしい堅実な議論を積み上げている点は傑出している。例えば第五部では好事家の注目を集めてきたネエ小唄を扱うが、その前に小市民歌謡やモガ歌謡を置くことでより広い視野を提供している。2024/05/18
-

- 電子書籍
- 闇金ウシジマくん【タテカラー】 ホスト…
-
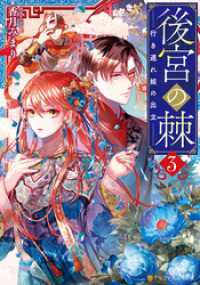
- 電子書籍
- 後宮の棘 行き遅れ姫の出立3 アルファ…
-
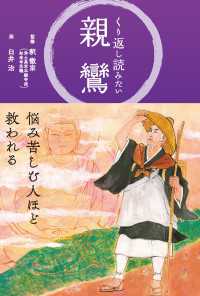
- 電子書籍
- くり返し読みたい 親鸞
-
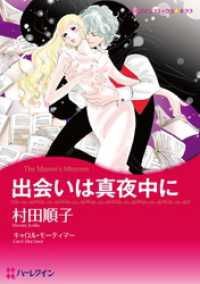
- 電子書籍
- 出会いは真夜中に【分冊】 7巻 ハーレ…
-
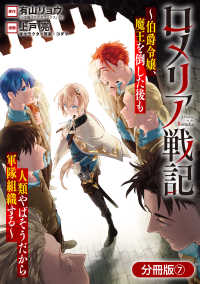
- 電子書籍
- ロメリア戦記~伯爵令嬢、魔王を倒した後…




