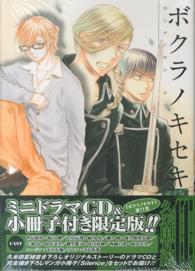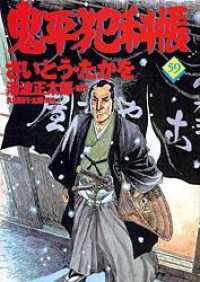内容説明
人間関係、ハラスメント、組織の運営からテロリズム、環境破壊まで、現代の諸問題を複雑系科学の立場から読み解き、しなやかに生きる術を明らかにする。
目次
第1章 知るということ(ちがいと情報のちがい;暗黙に知ること ほか)
第2章 関係のダイナミクス(コミュニケーション;ハラスメント ほか)
第3章 やわらかな制御(計画制御の困難;やわらかさの実現 ほか)
第4章 動的な戦略(無形―孫子の兵法;第一次世界大戦の衝撃 ほか)
第5章 やわらかな市場(「市場/共同体」という幻想の対立;共同体と市場の混合 ほか)
著者等紹介
安冨歩[ヤストミアユム]
1963年生まれ。91年京都大学大学院経済学研究科修士課程修了。京都大学人文科学研究所助手、名古屋大学情報文化学部助教授、東京大学大学院総合文化研究科助教授を経て、2003年より東京大学大学院情報学環助教授。著書に『「満洲国」の金融』(創文社、1997年、日経経済図書文化賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
takeapple
16
硬直した組織や考え方は良くない。ハラスメントを生む。近代化から取りこぼされたものに目を向けるものがある。特に今後複雑さを増して行く世の中を生き抜いて、より良い世の中にして行くにはそれが必要。大きな歴史の流れで考えると、現在成功しているものが最終勝者ではないよ。中国社会と日本社会を見ればわかる。近代化を全て良しとするわけでは無いけれど、アジア的なものが全て良いわけではない。色々な古典も読み方によって価値がある。いずれにしろ、同調圧力に屈し、異質なものを排除して行くようでは先がないと言うことか。また読みたい。2020/07/26
柳田
15
これはものすごくいい本だったと思う。著者の『生きるための経済学』『合理的な神秘主義』などまではよかったのだが、今は自己啓発的な本が多くなってしまって残念。2018/07/31
おおにし
14
ベイトソン、ポラニーの話から始まって、コミュニケーション論になるまでは何とかついていけたが、ここからハラスメント論への展開あたりで急に難しくなった。他人ごとではないモラル・ハラスメントについて、その実態や解決手段についてもっと詳しく触れてほしかった。この後出版された「ハラスメントは連鎖する」で詳しく書かれているようなので、次に読むことにする。2013/08/18
lendormin
6
まずは一周目。 人間は理性により自然を制御することに根本的に失敗している。それが完膚なきまでに露呈したのが第一次・第二次世界大戦であった。そこまでは20世紀の哲学の共通の認識だと思う(「人間は進化に失敗した」(アーサー・ケストラー))。 では理性によらずして、計画によらずして人はどうやって生きていくのか。われわれは何を間違い続けてきたのか。それを解くキーワードが「やわらかな制御」である。やわらかな制御、目的を手段に適合させよ、コミュニケーションの形成と複数化・活性化、無形、バーザール、ふむふむ。 2020/10/13
Hiroki Nishizumi
5
考えさせられる。特に計画制御は人間が関与する事態への適用が原則的に不可能との主張は深い意味を持っていると感じた。2018/12/20