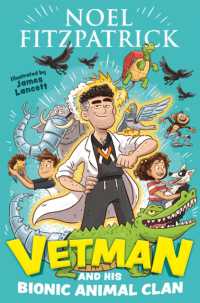出版社内容情報
20世紀は,かつてない課題を「法」に突きつけ,多様な法思想を生み出した時代でもあった.ケルゼン,ハート,ドゥオーキンらの法理論の流れを「言語論的転回」という視角から読み解き,概説する.実定法解釈学を学ぶ者も必読.
内容説明
20世紀という時代は、かつてない課題を「法」に突きつけ、多様な法思想を生み出した時代でもあった。ケルゼン、ハート、ドゥオーキンといった法思想家たちはいかにして「法の自立性」を確保しようとしたのか。また「言語論的転回」という思想史上の一大事件が法理論にもたらしたものは何か。こうした視角から20世紀法思想の流れを一つの物語のように描き出そうとする画期的な本書は、実定法解釈学への理解を深める上でも役立つ一冊となるだろう。
目次
第1章 20世紀法理論の出発点―ケルゼンの純粋法学
第2章 法理論における言語論的転回―ハートの『法の概念』
補論 ハート理論における「法と道徳」
第3章 解釈的実践としての法―ドゥオーキンの解釈的アプローチ
第4章 ポストモダン法学―批判法学とシステム理論
補論 脱構築と正義―デリダ「法の力」
第5章 むすび
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
じょに
5
これは名著。というか名教科書。ケルゼン・ハート・ドゥウォーキンのわっかりやすい解説から、ポストモダン法学としてルーマンやデリダへ。エヴァルドやルジャンドルなんかにも一瞬熱く触れられているくらい、周辺の諸理論も幅広く紹介されていて面白い。分かりよい教科書大好きでごめんなさい。2009/05/16
takizawa
3
「法の自立性」と「言語論的転回」という2つのテーマを軸としているので,思想史の教科書なのに,物語的に通読できるという点が素晴らしい。主な流れは,ケルゼン→ハート→ドゥオーキンorポストモダン法学。実践的な法解釈学に勤しんでいるロースクール生としては,法解釈とは何か,を問うて日々の疲れをとったらいいんじゃないでしょーか。(日々の疲れが溜まる一方だという説もある)2009/12/14
ぽん教授(非実在系)
2
法はほかの領域とどんな関係か?自立できるのだろうか?という流れとハートが20世紀の英米思想である分析哲学から持ち込んだ「言語論的転回」の二つの流れから見る法思想史。ハートを中心に、その前段階であるケルゼン、ハート以後であるドゥオーキンを主に扱いつつ、批判法学は法帝国主義的なドゥオーキン批判を、ハートをベースにしながらも新しく展開する流れとしてみているようだ。ニコラス・ルーマンやデリダを法思想の立場でみるとこうなるのか、という知見は自分の分野的にはかなり新鮮で面白い。2016/11/19
きみどり
0
法思想史のテキストを読むと、ソクラテスやプラトンから始まってローマ法やらカントやら、フランス革命やアメリカ独立宣言でどうこうやら、と、なかなか現代まで辿り着かず、やっと到達したその頃には疲れ果てて(飽きて)いる…… という自分のような人にもぜひ。内容はハイレベルでも、わかりやすい記述で読ませます。ケルゼン、ハート、ドウォーキン、ポストモダン法思想の流れが軸になっていて、それとは別に、大陸法理論や正義論、マルクス主義法思想などの周辺分野をコラムとして立てるという構成です。2013/02/11
えむ
0
二十世紀の法思想を、法概念論を中心に幅広く検討。ケルゼンからCLSまで、扱われる思想の領域は広く、かつ分かりやすくまとまっているので非常に有益である。また、巻末の読書案内も充実しているので、現代の法思想を学びはじめるための1冊としてもよくできていると思う。2018/10/07