内容説明
冒険する少女たちの目はなにを見たのか。19世紀ヨーロッパの物語に登場した新しい少女の群像。「アリス」誕生の謎をさぐる異色の児童文学史。
目次
1 『人魚姫』を読みなおす(ひっくり返った『人魚姫』観;王子へのあこがれの意味 ほか)
2 よみがえった伝承世界(水の精としての人魚姫;先駆けとなった『ウンディーネ』 ほか)
3 妖精という言葉の魔法(一八六五年という年;『不思議の国のアリス』誕生前夜 ほか)
4 少女の目の発見(アリスという少女;対位法的展開の魅力 ほか)
著者等紹介
脇明子[ワキアキコ]
1948年、香川県生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。ノートルダム清心女子大学名誉教授。「岡山子どもの本の会」代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かりさ
52
英国ファンタジー翻訳、研究家である脇さんの視点と考察から19世紀児童文学史を読み解く。人魚姫の男装、水の精、妖精と魔法、幻想性と神秘性、ファンタジーの中の少女の秘めた思いや願い…物語を深く知り寄り添う楽しさを得ます。アンデルセン「人魚姫」、マクドナルド「かるいお姫さま」、キャロル「不思議な国のアリス」など19世紀ファンタジーで描かれる少女たちの群像を共に辿り、深い考察と新しい視点で、物語の生まれた時代やその背景を知る…新たな扉を開けたような新しい風が吹き込むような新鮮な思いで読みました。2021/03/10
シルク
24
こどものとき愛した物語のひとつに、J・マクドナルドの"The Light Princess"がある。あんなに好きだった話であるのに、大人になってから本を手に取ると、訳(読んでいたのは本庄冨美恵訳)に感じられるねっとり感が気持ち悪くて、読み進められない。どんな話だったかな……王様と女王様に、ようやく生まれた娘が主人公だ。魔女である叔母の呪いで、体重というものを持たない子だ。ふわんふわん浮かんで、そしてその性質もか・るい軽い。彼女はケタケタと笑う。深く考えることも何かを悲しむことも無い、ただ愛らしいだけの姫。2018/02/11
おゆ
16
自由な尾ヒレを捨てて痛む脚を手に入れた人魚姫。原作では男装していた姫の行動力、けれど男性社会で歩く自由を手に入れた彼女は、弱音を吐くための声を持たない。美しい歌声で船人を惑わすセイレーン、彼女もその種族の一人であったのに。最期は望み潰え泡と消えた姫。けれど彼女が本当に望んだのは王子の隣の席ではなく、王子の持つ自由さそのものではなかったか。その王子が選んだ王女は美しく優しい女性だが、完全無欠のカップルに漂うこの空虚感はなにゆえか。魂を持たないはずの水妖が体現してみせる、19世紀の少女たちの夢と憧れ。2018/04/12
なつき
13
『人魚姫』の考察が非常に興味深い。訳と思い込みから可憐な人魚姫しか知らなかったが、確かに人間になったとしても『女性』では当時それほどの自由はない。彼女が憧れていたのは二本の足でどこにでも行ける『男性=人間』だったと。男装のサンド、水の妖精ウンディーネ、アリスと少女論は続いていきますが、もう少し一つ一つをじっくり読みたかった気もする。例示が多く結論が薄い、そんな印象。出来れば『人魚姫』論を深めて、泡になる結末までしっかり論じてほしかった。2014/02/22
くさてる
12
アンデルセンの「人魚姫」の解釈がとても新鮮で面白かった。そういう感じで、童話や当時の物語に描かれた少女像の読み解きの部分がもっと読むことが出来れば嬉しかったです。2014/03/16
-

- 電子書籍
- 私の身体を濡らせたら 7巻 メルティル…
-
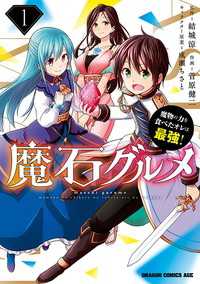
- 電子書籍
- 魔石グルメ 魔物の力を食べたオレは最強…
-

- 電子書籍
- 憂鬱な花嫁【分冊】 9巻 ハーレクイン…
-

- 電子書籍
- さびしい結婚【分冊】 3巻 ハーレクイ…
-
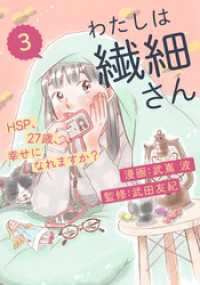
- 電子書籍
- わたしは繊細さんーHSP、27歳、幸せ…




