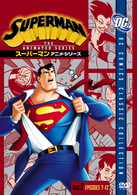出版社内容情報
古代から近代の西洋美術と日本美術における光と闇の相克の歴史を、カラヴァッジョ研究の第一人者が読み明かす。
内容説明
あらゆる美術は光の存在を前提としている。だが、革新性は闇によってもらたらされた。一七世紀イタリア、“光と闇の天才画家”カラヴァッジョの登場は、絵画に臨場感という衝撃的なドラマを生んだ。古代から近代の西洋美術、そして日本美術における光と闇の相克の歴史を、カラヴァッジョ研究の第一人者が読み明かす。縛る+放つ―闇の存在なしにドラマは生まれない。
目次
第1章 闇の芸術の誕生
第2章 光への覚醒―カラヴァッジョの革新
第3章 ドラマからスピリチュアルへ―カラヴァッジェスキとラ・トゥール
第4章 バロック彫刻の陰影
第5章 闇の溶解、光のやどり―レンブラントから近代美術へ
第6章 日本美術の光と闇
著者等紹介
宮下規久朗[ミヤシタキクロウ]
1963年名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業、同大学院修了。現在、神戸大学大学院人文学研究科教授、美術史家。2005年『カラヴァッジョ 聖性とヴィジョン』でサントリー学芸賞、地中海学会ヘレンド賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
383
タイトルの「闇の」は、比喩ではなく、文字通り光と闇という時の光学的な闇。中世以前は、神および神の恩寵は「光」そのもので表現された。例えば、ヴェネツィアのサン・マルコ大聖堂の天井画やラヴェンナに残るキリスト像などは金で装飾されているし、またシャルトルをはじめとしてステンドグラスは聖堂内に光をあふれさせた。闇が描かれた最も古い例として(ただし、それは光を強調するためであった)14世紀のガッディ『羊飼いへの告知』が紹介される。闇が、闇そのものとして主体的に描かれたのはやはりカラヴァッジョということになる。⇒2021/03/26
KAZOO
120
闇の美術ということで光と影をどのように絵画に表現してきたのか、ということを結構有名な画家の作品を通して解説してくれています。カラバッジョから始まり、ベルリーニ、ラ・トゥール、フェルメール、レンブラントなど私の好きな画家の作品が掲載されています。日本の画家で山本芳翠という人が、ラ・トゥールと似たような絵を描いているのには大発見でした。2016/12/02
鉄之助
113
転職を考えているときに、この本に出会えて本当によかった。 1600年、カラバッジョが描いた「聖マタイの召命」。彼のデビュー作であり、次の美術史の扉を開く記念碑的作品、この本の表紙を飾っている。マタイがキリストの啓示を受け天命を知ったマタイの決定的瞬間を描いた絵画だが、誰がマタイなのか論争となっている。この本を読み、「天命とは? 天職とは?」、を考えさせられた。結論は、天職とは、与えられるものでなく、自らが感じるもの。これから始まる、新しい仕事を天職と、思い定めて頑張りたいと思っている。2024/09/29
夏
34
去年著者の講演会に行く機会があったのだが、それがものすごく面白かった。講演が面白いなら本も面白いだろうと思った通り、本書もすごく面白かった。この本を読むまで、絵画において闇をあまり重視していなかった。闇というよりも、闇から浮かび上がる光の方に目を奪われていたからだ。けれど、闇があるからこそ光が明るく思えるのだということに気づかされた。本書は闇の芸術の誕生からカラヴァッジョへ、そしてカラヴァッジェスキ以降へと展開していく。最後は日本美術における光と闇が語られており、読み応え十分となっている。星4.5。2024/05/31
あーびん
29
光は古来から太陽とともに、神と同一視されてきた。西洋絵画や教会建築では神を光として表現し、光と闇の対比の効果を追及してきたが、カラヴァッジョの登場は17世紀のほとんどの画家にその影響を及ぼした。カラヴァッジョ様式の特徴は理想化を排した自然主義であり、聖人がリアルな民衆の姿で描かれ聖書のできごとが同時代で起こっているような斬新な写実主義である。また、その闇の強い様式はテネブリズム(暗黒主義)といわれ、カラヴァッジェスキに広く好まれた。ベラスケス、レンブラント、フェルメールなどにも受け継がれた光と闇の表現。2020/11/07