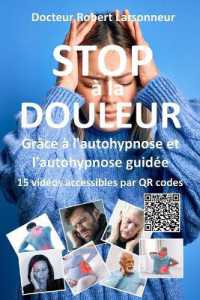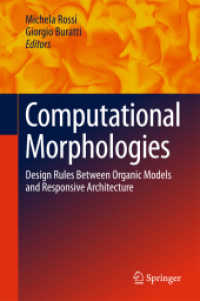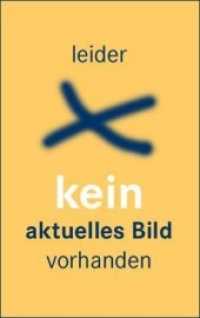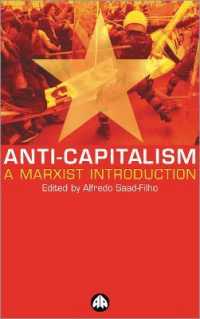出版社内容情報
民俗学と民族学の両方を研究分野としてきた著者は,柳田と梅棹という強烈な個性と関わってきた.二人の知のスタイルは,西洋の学問に依存せず,自分の目で見,耳で聞き,身体で感じ,自分の頭で思考することだった.稀有なリーダーシップによって学問の場をつくりあげた二人
内容説明
民俗学と民族学の両方を研究分野としてきた著者は、柳田国男と梅棹忠夫という強烈な個性と関わってきた。ふたりの知のスタイルは、幅広く多くの文献を参照しつつ、西洋の学問に依存するのではなく、自らの頭で仮説を構築して思考することだった。稀有なリーダーシップによって学問の磁場をつくりあげた両者の研究にまつわる数々のエピソードから、今日の学問状況を考える。
目次
序章 ふたりの日本研究
第1章 晩年の柳田国男回想
第2章 民博時代の梅棹忠夫回想
第3章 ふたりのリーダーシップ
第4章 ふたりの交錯する思想
第5章 ふたりの日本研究の課題
終章 ふたりの知のあり方点描
著者等紹介
伊藤幹治[イトウミキハル]
1930年東京都に生まれる。1953年國學院大學大学院文学研究科修士課程修了。国立民族学博物館名誉教授。文学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
5
民俗学と民族学(文化人類学)。共に現代日本文化において重厚な学問の印象。「常民」という人びとの存在。日本文明と他の文明との比較をする「文明の生態史観」というものの見方(13ページ)。評者も拙稿の出発点は、限界集落で民俗的なテーマ、いわば社会学であるが12年前を想起した。柳田先生は語りもの的なことばを使った(42ページ)。飯田市美術博物館の柳田国男館は訪れてみたい(47ページ)。梅棹先生は文化を文明の一つと見做した(90ページ)。「型くずしの学問」(131ページ)。二人とも自前の学問を創った。独創は困難だ。2012/12/07
かりん
3
3:著者がつむぐ二人の共通点が興味深い。年齢的なこともあるでしょうが、著者の二人への尊敬度合いには差があるよね(笑)。■伝統は近代化につながらなかったのではない。つながなかったのである。科学には三つの要素がある→実証性、仮説性、体系性。体系性が強くない。母にわかる文章。ワンマンでないとこうははっきり出せない。明治維新以後今日にいたるまで、日本文化論や日本思想論をつらぬく基本的モチーフは、自己批判であったといってさしつかえない。ふたりは欧米からの借り物でない「自前の学問」を構築しようとしていたのである。2011/05/21
mikyao2006
2
クロスオーバーする二人の思想。ともにオリジナル。2013/09/22
メルセ・ひすい
2
15-40 もうこの世にはいないが…強烈な個性…の柳田、梅棹先生 二人の知のスタイルは、幅広く多くの文献を参照しつつ、この国で自らの頭脳で仮説を構築しつつ思考を重ね、研究を進めてきた。稀有な研究にまつわる数々のエピソードとは? そして今日の学問の継承は… ダブル評伝。2011/07/23
とまる
1
欧米から学んで前進してきた日本。でも、それでは掬い切れない部分もある。借り物ではない自前の学問を掲げた2人。印象に残ったのは学問と実用性の話。欧米では目的地への「行進の美」が評価されるのに対し、日本には目的地の無い「漂流の美」を崇高とする精神がある と言う梅棹氏の「無用の用」。研究の実用性を訊くと侮辱されたような顔をする学者が居るが 学問を世のため役立てることは誤りではないハズだと言う柳田氏の「有用の用」。有用性というのは(特に文系の)学問をする者が必ず当たる壁かもしれない。2012/02/01
-

- 電子書籍
- 俺専用夢境【タテヨミ】 135話