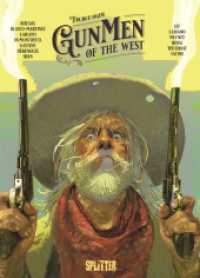- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
「岩波文化」という言葉さえ生みだした岩波書店の出版活動は、敗戦をまたいだ一九三〇年代から六〇年代にかけて最高潮に達した。戦前の『日本資本主義発達史講座』の刊行、新書の創刊、津田左右吉事件、戦後の『世界』の創刊、昭和史論争など重要な論点をたどりながら、国民国家日本の「人を教育する文化」を担い続けた軌跡をたどる。
目次
第1章 「教育国家」の学術出版社
第2章 学術出版社のネットワーク
第3章 「非常時」の出版革命
第4章 総力戦下の読書文化
第5章 国内思想戦と言論統制
第6章 悔恨共同体の文化
第7章 戦後啓蒙の射程と限界
第8章 午後四時の教養主義
著者等紹介
佐藤卓己[サトウタクミ]
1960年生。京都大学大学院教育学研究科准教授。専攻、メディア史。著書『『キング』の時代』(2002、岩波書店、日本出版学会賞受賞、サントリー学芸賞受賞)、『言論統制』(2004、中公新書、吉田茂賞受賞)、など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
12
ワーヅワースの「低くくらし、高く思ふ」(3頁)。1915年の『京都帝国大学新聞』創刊号の下半分の広告が、岩波書店刊行書から成っているという、京大との関係も深いことがわかる(5頁)。漱石文化に立つ岩波的ジャーナリズム(9頁)。岩波文化は、官民関係のあるべき姿を提起する(10頁)。岩波書店の活動は、戦後の総合雑誌と女性、子ども向け読み物を除いて全ジャンルに及ぶ守備範囲の広さを誇る(90頁)。新書は岩波が嚆矢(115頁)。今では多くの出版社が新書ラッシュで新刊棚が賑わう。文庫モデルは独レクラム文庫(117頁)。2014/01/12
やまやま
9
戦中において兵士に慰問のため配布された岩波文庫は他を圧して巨大なものであったが、それは用紙配給を多く受ける因果とも言えるし、徴用外でも「慰問袋に岩波文庫」の標語を自社で掲げていたように、軍部から強制されることなく軍部に寄り添う出版文化を「教育」の時代の一コマとして語りたかったように伺えた。戦中と戦後で「戦場での読書行為」の解釈は変容し、典型的な戦後的解釈は「きけわだつみのこえ」とされる。編集は反戦平和を志向したとしても、遺稿では死に直面して安心を求める読書姿勢も多く描かれていたことを丁寧に整理している。2020/12/27
takao
2
ふむ2021/01/07
rbyawa
2
j020、古い本見られる「講談社と岩波書店の対立」というものは学者の空論の一つ、と思っていたら岩波書店の社長が本当に講談社を見下した発言をしてがっかり。本の中でも語られていたけれど、年齢層が上なだけで高尚な内容かというと疑問だよなぁ…「頑張れば労働者でも読める」だよね岩波…。教育を行うメディアであることは変わらないよね、という現代の主流まで触れてくれているのである意味で向き合わないとならない過去の遺物の本だったのかもね。しかし、検閲で難解になった文章こそがインテリって…定番の似非インテリ、乗るなよ社長…。2019/02/21
doctor bessy
0
岩波書店の歴史というより、大戦前後の言論統制及び思想史文献として読んだ。1940年代も繁盛したようだが、岩波書店の本はどんな人が何の目的のために買い求めたのだろうか。 「君たちはどう生きるか」を出版当初に読んだ人たちと、ジブリ映画を鑑賞した人たちは、どれぐらい違っていて、どれぐらい同じだろうか。2025/10/10