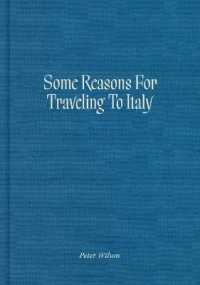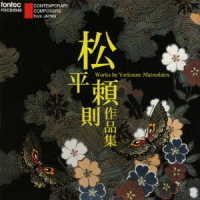内容説明
踊りをもっと愉しんでいただきたい―そんな思いを込め、踊りの名手・十代目坂東三津五郎が、魅力あふれる舞踊の世界へご案内いたします。日本舞踊の本質や心得、身体の使い方や振りなどの知識から、三津五郎代々の藝、稽古の思い出まで、明晰な語り口で説き明かします。坂東家の藝である『道成寺』『六歌仙容彩』『山帰り』『三社祭』『棒しばり』などは演目ごとに解説。
目次
第1章 舞踊の本質(スポーツと比較する;舞台へ出るときの心得;鏡を見る稽古は禁止です;上手い下手の大きな分かれ目;踊りの振りのさまざま;身体との会話;劇場空間を把握する;踊りの起源)
第2章 私の踊りをつくってくれた人々(坂東三津弥さんのこと;坂東流の流儀;芸事の上達;明治生まれのお師匠さん;十代にうぬぼれはありません;流儀の運営について;振付けることで学ぶ;踊りの上手になりおおせるために)
第3章 踊りのさまざま(『道成寺』;『山帰り』;『六歌仙容彩』;『文屋』;『喜撰』;『靱猿』;『傀儡師』;『流星』;『玉兎』;『供奴』;『舌出し三番』;『大原女』;『三社祭』;『棒しばり』)
著者等紹介
坂東三津五郎[バンドウミツゴロウ]
歌舞技役者・日本舞踊坂東流家元。昭和31年九代目坂東三津五郎の長男として東京に生まれる。昭和32年「傀儡師」で曾祖父七代目坂東三津五郎に抱かれて初お目見得。昭和37年「黎明鞍馬山」牛若丸役で五代目坂東八十助を名乗り初舞台。平成13年十代目坂東三津五郎を襲名。平成18年日本芸術院賞、平成21年紫綬褒賞など受賞多数
長谷部浩[ハセベヒロシ]
演劇評論家、東京藝術大学美術学部教授(近現代演出史)。昭和31年埼玉県に生まれる。慶應義塾大学卒業。現代演劇・歌舞技を中心に評論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぶんこ
筋書屋虫六
クリイロエビチャ
コユキ キミ
Sae