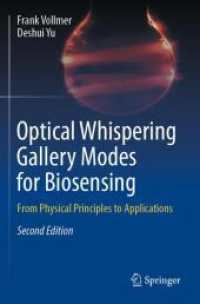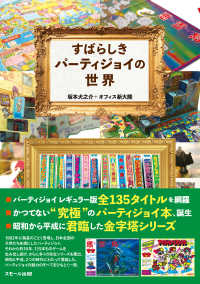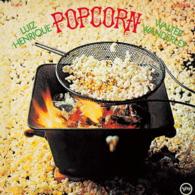出版社内容情報
戦後日本を代表する知識人・鶴見俊輔は、民主主義と平和主義を社会に根づかせる積極的な役割を果たした人と目されながら、一方でそれらに対する懐疑を抱き続けていた。日常性に根ざす思考に可能性を見いだし、「新しい知」のあり方を模索し続けた鶴見が、彼方に見ていたものは何だったのか。その豊饒なる思想世界の解読に、「いのち」をめぐって問いを積み重ねてきた著者が挑む。
内容説明
日常性からの志、希望のありかを求めて。「新しい知」のあり方を模索し続けた哲学者の、豊饒な思想世界を読み解く。
目次
序章 正義と狂気のあいだ
1 反戦の思想と行動(一九六九年八月・大阪城公園;大東亜共栄圏とハンセン病;反戦と好戦のあいだ)
2 新しい知を求めて(民族主義のパラドックス;戦後民主主義のルーツ;ローカルな普遍性)
資料 鶴見俊輔の石川三四郎宛書簡三通
著者等紹介
高草木光一[タカクサギコウイチ]
1956年群馬県生まれ。慶應義塾大学名誉教授。社会思想史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
38
母と鶴見さんが亡くなったのは2015年であった。あれから10年。。広島原爆投下の日に、T図書館より拝借。土民生活と市民生活(35頁~)。この土民生活はデモクラシーとルビがある。寝泊まりする土着の民。市民は反博覧会イベントの対応のみ(34頁)。土民は農民も含む。他人を搾取しない(37頁石川三四郎)。私は市民大学院に関わったときは、教授も、社会人研究者も、フラットな目線を意識して活動していたと思う。癩病というのは、戦争癩が軍人癩と同義で、戦中や戦後直後、よく使われたという(藤野豊、62頁)。2025/08/06
踊る猫
30
鶴見俊輔という存在をいたずらに神格化し「無辜のカリスマ」と褒め殺すのではなく、かといって後出しジャンケンの理屈で雑駁にこき下ろすのでもなく、フェアネスを貫き彼が残した仕事を読み込み為した功績を評価していく営み。そのおそるべくねばり強さが必要とされる試み(容易にわかるように「是々非々」が要求されるわけだから)を、高草木は実に手堅い筆致とアプローチで為している。ここから見えてくるのは時に矛盾や破綻を見せつつ、その内面に迷いなども抱えつつも同じようにねばり強さを以て「反戦平和」を追究し続け、奮闘した知識人の姿だ2024/10/15
Go Extreme
2
鶴見俊補の「反戦の思想と行動」 1968-69年・大学闘争ー思考転換点 「民間学」ーアメリカ哲学の相対化 1969年8月・大阪城公園: 反戦運動「べ平連」 小田実と活動・死後も思想継承 平和運動の単純な「正義」化に疑問 大東亜共栄圏とハンセン病: 理念を批判→日本国内の文化的差別 平和運動と社会的差別問題を関連付け 反戦と好戦: 反戦運動過激化と社会変革先鋭化 ベトナム戦争を批判・広範な社会的変革 戦後民主主義: プラグマティズム ディスコミュニケーション ローカルな普遍性: 歩く学問による新たな知の探求2025/02/03
tu-ta
1
PP研戦後研のテキストということで図書館で借りた。鳥取の菜の花診療所の徳永進と鶴見俊輔の関係をこの本で初めて知った。この徳永のべ平連のスタンスに対する問題提起も興味深し、開高健との関係を描く3章「反戦と好戦のあいだ」も興味深かった。返却する関係でところどころ飛ばし読み。 ここに書いたものをまとめたのが https://tu-ta.seesaa.net/article/504127545.html2024/07/25