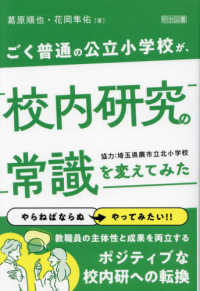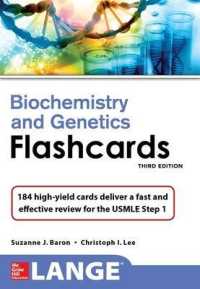出版社内容情報
「長い一九世紀」──フランス革命から第一次世界大戦までの約一二五年間に、国民国家と植民地帝国はいかに形成されたか。本国と植民地および国内辺境の相互関係に着目しながら、海域の変容、奴隷制の転換と移民の急増、人種主義・ナショナリズムの醸成により、「国民」や「国家」の境界が定められ再編されていく複雑な過程をとらえる。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さとうしん
14
北村氏の展望ではフランス革命の起点に諸説があること、西欧諸国の植民地獲得の動機について「文明化の使命」が注目されていることなどが示唆されている。「文明化の使命」は、並河論文によると英仏による奴隷制廃止の拡散にも影響したとのこと。「文明化の使命」はまた、中澤論文で触れられる西欧のスロヴァキアなどに対する「歴史なき民」という視線とも関係するであろう。貴堂論文では、「移民国家」の印象が強いアメリカではあるが、南北戦争の頃までは「奴隷国家」「奴隷主国家」と位置づけるべきであるという議論を紹介する。2024/01/18
MUNEKAZ
13
「長い19世紀」に関する認識のアップデートにはちょうど良い一冊では。国家体制の変容やジェンダー関連、ユダヤ人に関する話題などドイツに言及した章が多めかな。また総論を書いている方がイタリア史の専門なので、英仏に偏らずイタリアに関する言及が多めなのがちょっと新鮮な印象。両国とも19世紀に「生まれた」強国であり、時代精神を代表するところがあるのかもしれない。奴隷は開放するけど移民は酷使する。「文明化の使命」を唱えながら植民地を獲得する。この理想と傲慢のダブスタ具合が帝国主義の時代らしいところである。2024/02/21
かんがく
11
展望だけちゃんと読んで、残りは流し読み。フランス革命から1848年革命を経て第一次世界大戦に至る「長い19世紀」についての最新研究を概説。革命と戦争の中で国民統合の統合が進み、自由主義や民主主義、人権、解放などが声高く宣言される一方で、奴隷貿易、植民地支配、疑似科学などの暴力的な側面ももつというのが時代の特徴。2024/03/04
なつきネコ@着物ネコ
8
前に読んだマーシャと白い鳥のお話の別作者の本だったのか。題名が違うから気づかなかった。しかし、イラストが違うと与える雰囲気が違う前のマーシャと白い鳥は激しく大冒険みたいにみえていたけど、このイラストでは等身大のマーシャの冒険みたいにみえる。良い意味でリアリティがあって、兄弟なりの冒険を繰り広げて、帰ったんだなと思える。2022/07/15
ポルターガイスト
3
タイトルから期待したとおり「統合と分化」について一面的な理解を揺さぶる刺激的な論考が多くよかった。特に移民,近代奴隷制,ユダヤ人について扱ったものは授業づくりの参考になったと思う。授業のなかで19世紀の国民形成という主軸をしっかり叩き込みつつ(それがないと混乱だけに終わってしまう子が多くなるから。安心させるために)それと矛盾する動きが糾える縄の如く交錯していたことにどれだけ気づけるか。喉に引っかかる骨を取り除いてやりつつも,認知的不協和に耐える訓練が必要になる。2024/03/31