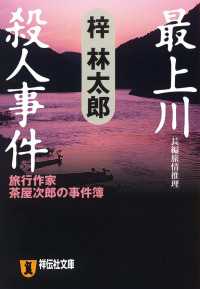出版社内容情報
子どもの学習体験や内面のドラマに深くふれることから教育は始まります.著者は臨床心理学の造詣と教育現場との交流を生かして,子どもの個性が生きる新しい教育のあり方を大胆に提起します.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
10
カリキュラムをもとに「育てる」という戦後教育は、教育現場で起こる事象を問題として解決を目指す。一方臨床教育は、事象を個々の生徒が発する心理的危機の兆候として扱い、「育つ」側である生徒主体の立場を採る。臨床教育学の日本初の書籍化である本書は、臨床家の著者が思春期までの子どものカウンセリング事例を挙げ、事象を偶発的な問題として処理するよりも、偶発性を受け入れつつ咄嗟に判断して行動する必要があると語る。その際臨床家は、可謬主義的で試行錯誤する弱い論理(仮説)を用い、真理を目指す強い論理(演繹)から距離を取る。2023/03/01
T
5
様々な事例が紹介されており、具体的なばかりか、河合隼雄先生の柔軟で示唆に富んだ解説で読みやすい。中でも今回特に考えたのは、大人は思春期の子どもの「壁になる」こと、無制限の自由は不自由であり「容器」としての規則が必要だということ。どちらもただ放任で無制限の「自由」を与えればよいというのではなく、壁になったり容器になったりして、思春期の子どもにぶつかり合うことの大事さが説かれていた。壁と言っても、ただ思いを却下するのではなく、血の通った壁でいなければならない。遊びの重要性も唸った。都度読み返したい。2018/03/25
優翔
4
ほぼ初めて読む分野だったので、時間がかかってしまいました。でも、なるほどと思えたりして、おもしろかったです。教育はやっぱり生徒と先生の距離感も大切ですが、家族関係も大切で、人間関係の重要性に気付きました。2014/03/09
きよまる
2
研究の第一歩。河合さんの著書をまるまる読むのは初めて。勉強になりました。臨床から教育を考えるなら、第一に大切にすべきは子どもの個性。そのために周囲の大人は壁になるべき。父性と母性。二項対立ではなく、どちらも正しい。欧米との比較なんかは私も見習わなければ。2016/06/14
ハリー
1
教師を目指しているので、読みました。 個性や、教育について河合先生がヒントを下さっています。 子どもについて、もっと言えば人間について、無知であると気づかされました。新しい発見がたくさんあるし、考えさせられることもたくさんあります。 「教」と「育」のお話は印象的でした。これからはもっと「育」の面を考えていく時代だと思います。子どもを科学的・客観的に見るのではなく(もちろんそれが必要な場面もありますが、)一人一人の個性を持った人間として大切にしてあげたいと思いました。



![Google Pixel便利すぎる!テクニック - 便利な機能や正しい設定、必見の裏技が満載! [テキスト]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48663/4866366885.jpg)